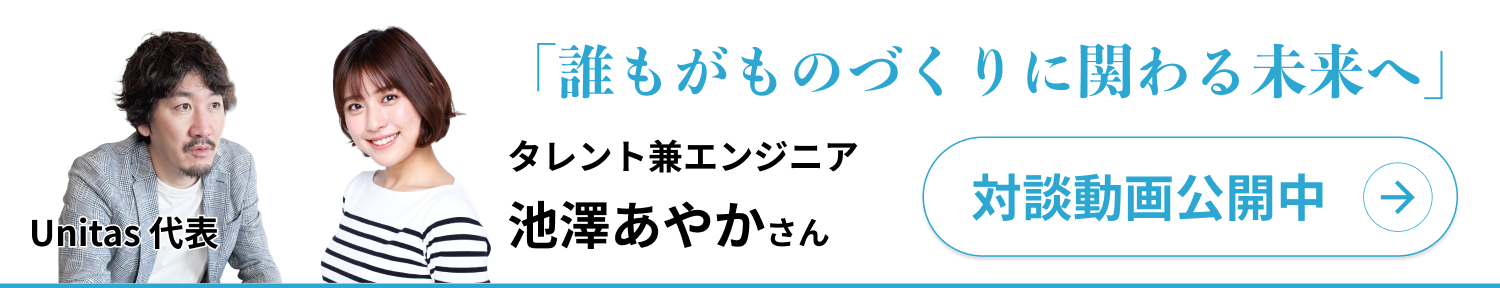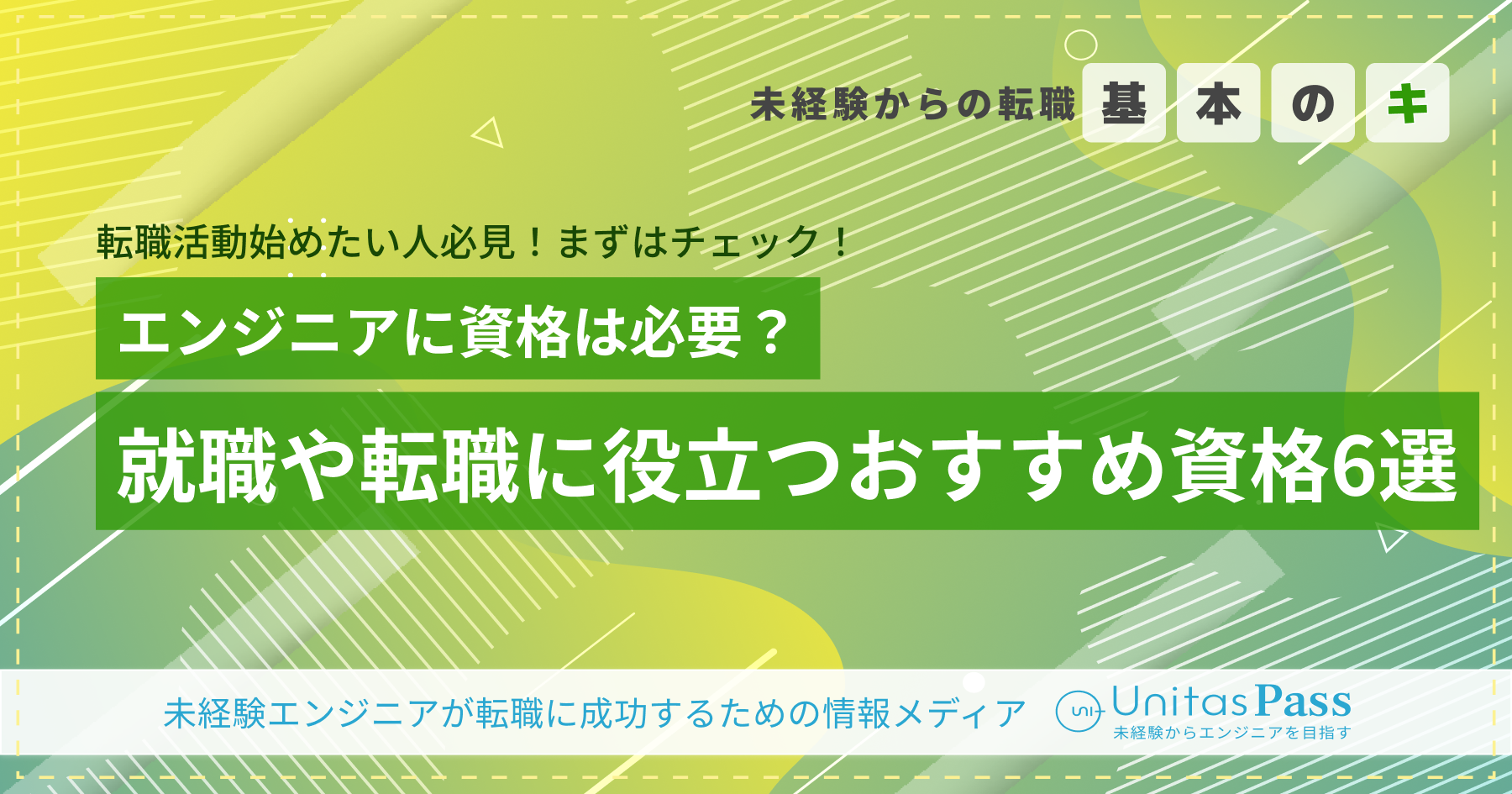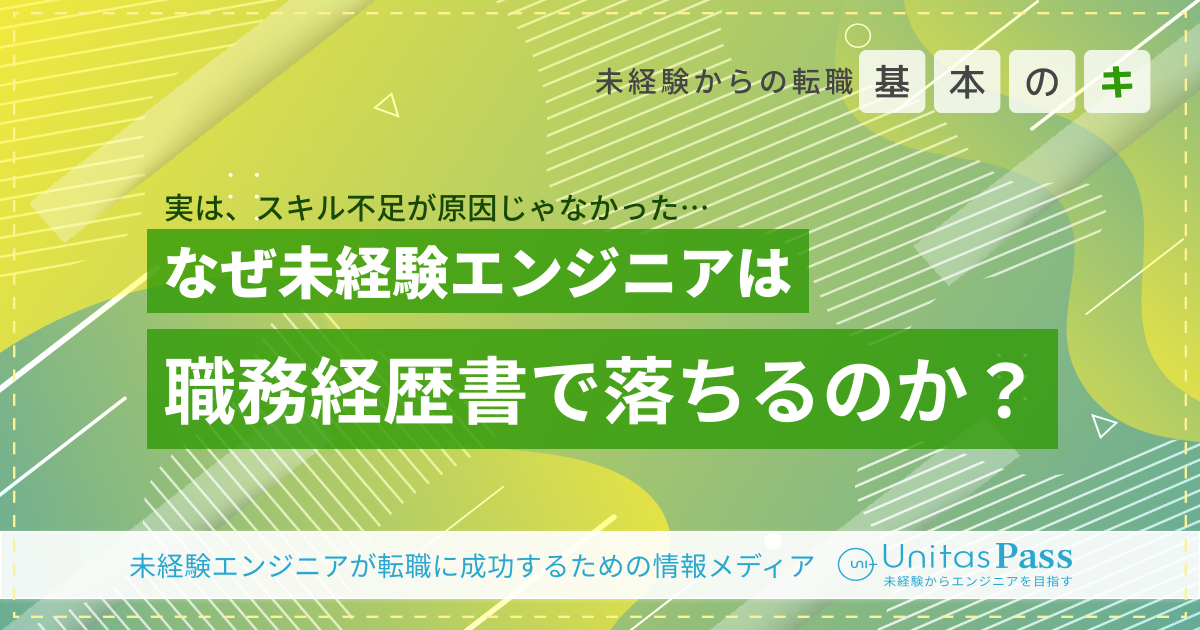【Unitas(ユニタス) 転職アドバイザー菅原さんが解説】伝え方が重要!ブランクを強みに変える書類・面接対策
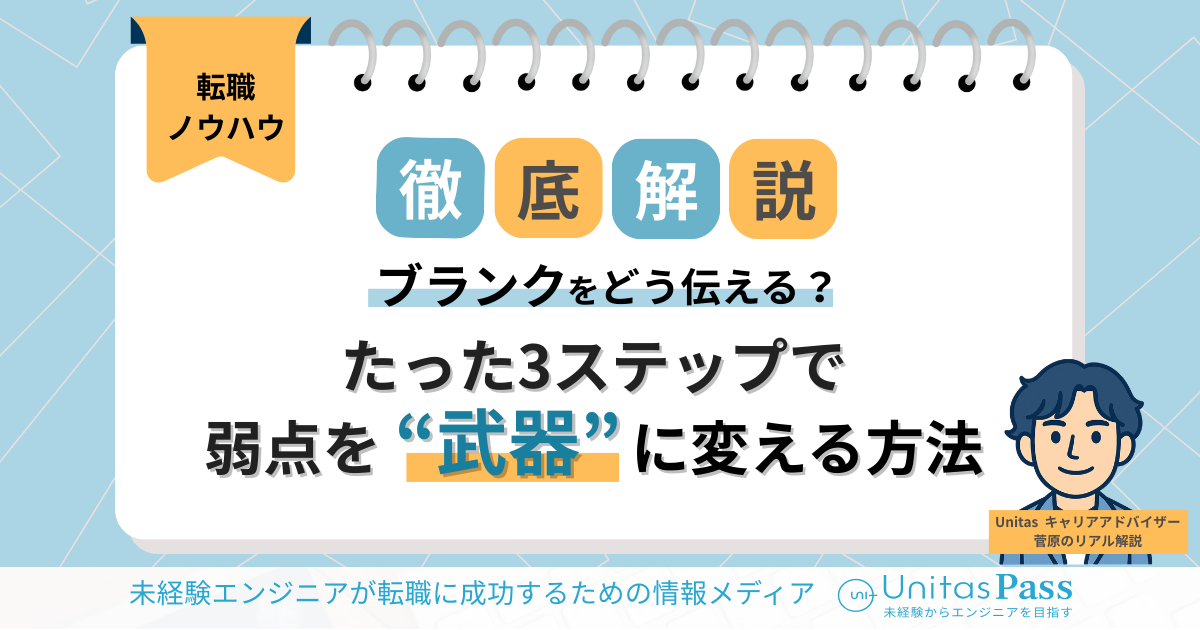
前職を退職してから次の職に就くまでの空白期間、いわゆる「ブランク」がある場合、「その期間に何をしていたのか」は、面接で必ず聞かれることになります。こうしたブランクは、マイナスポイントになりがちですが、理由やその間の取り組みを整然と伝えることができれば、印象は大きく変わります。
この記事では、豊富な経験を持つUnitas(ユニタス) 転職アドバイザー菅原さんのコメントを交えながら書類・面接でブランクを“強み”に変える具体的な対策を紹介します。
企業はブランクをどう感じる?

企業がブランクについて質問するのは、「入社後にすぐ戦力となれるか」という懸念があるからです。長い空白期間があると、スキルや知識が時代遅れになっていないか、キャッチアップできるかを不安視されがちです。
また、人事担当者の立場からは、仕事へのモチベーションが低いのではないか、環境に馴染めず早期退職してしまうのではないかという心配もあります。つまり、ブランク自体が問題なのではなく、その背景や今の姿勢をどう説明できるかが評価の分かれ道となるのです。
キャリアアドバイザー直伝!ブランクを強みに変える方法

ブランクがある場合、転職活動においてその期間に関する質問を避けることはできないと思った方が良いでしょう。しかし、実は面接官が本当に気にしているのは「その期間に目的を持って動いていたかどうか」です。
単なる“空白”ではなく、何らかの目的や学びがあった期間だということが伝われば、むしろポジティブに評価されるケースも少なくありません。
採用担当者に、ブランクの「理由」と「今後の展望」を説得力をもって伝えることが出来れば、大きなハードルにはならないのです。
ここでは、Unitas(ユニタス) 転職アドバイザー菅原さんのアドバイスを交えながら、ブランクを強みに変える方法を解説します。
おすすめ記事:SES案件ガチャって?配属先のリアルと回避法
①ブランク期間にしてきたことを整理する
まず重要なのは、ブランク中に取り組んだことを整理することです。例えば資格取得のための勉強に励んでいた場合は、学習した内容や取得した資格を具体的に示すことで、自己研鑽に努めていた姿勢を伝えられます。
育児や介護といった家庭の事情で働けなかった場合でも、その中で得られたスキルや気づきを言語化することが大切です。限られた時間の中で工夫して行動した経験や、他者を支える中で養った責任感や調整力は、ビジネスの現場でも十分に活かすことができるでしょう。
もし特に目立った取り組みがなかった場合でも、「この期間を通して自分のキャリアについて真剣に考え直した」「健康を回復させ、再スタートの準備が整った」といった気づきを伝えれば、主体性をアピールできます。
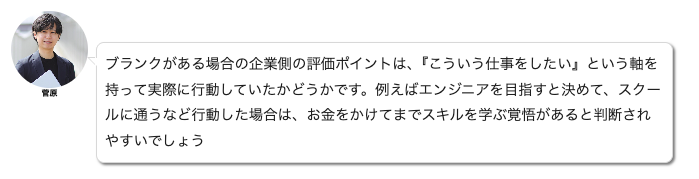
②ブランクをポジティブに転換する
次に大切なのは、ブランクの期間をポジティブなものに転換し、伝えることです。たとえば、ブランクの理由が育児であれば、「限られた時間の中でも継続的に学習を続けることができた」と学習習慣や責任感をアピールできます。
あるいは介護であれば、家族を支える中で培った調整力や柔軟性を強調するとよいでしょう。病気療養の場合は、完治していることや再発リスクがないことを明確に伝えることで、企業が安心して受け入れられる材料になります。
一方、「特に何もしていなかった」という人もいるかもしれません。その場合も、正直に伝えつつ「今はなぜ働きたいのか」「これからどう行動するのか」を明確に示すことが重要です。ブランクをただの“空白”で終わらせず、未来への意欲につなげることが信頼につながります。
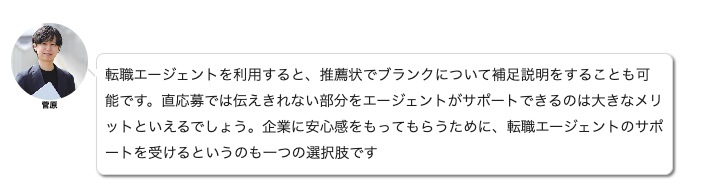
③ブランクの伝え方を工夫する
最後に欠かせないのが、ブランク期間の理由、過ごし方の「伝え方」です。面接でただ「介護をしていました」と事実だけを述べるのではなく、「その中で家族と学習の調整力を養った」と付け加えることで、経験をプラスの印象に変えられます。
つまり、「事実+得たこと」をセットで語ることが重要になります。さらに、「学んだことを次の職場でこう役立てたい」と未来への意欲と結びつけることで、前向きな印象を与えられます。
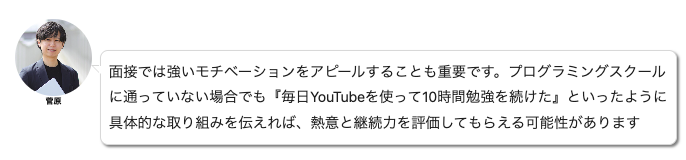
このようにブランクは「突っ込まれる弱点」ではなく、伝え方次第で「経験値」に変わります。理由を整理し、得たことを言語化し、未来への意欲と結びつけること。これこそが、企業の不安を解消し、むしろあなたの魅力を引き出す最良の方法といえます。
ブランクを強みに変える書類の書き方

転職活動において、履歴書や職務経歴書は第一関門です。特にブランクがある場合、書類上で「どのように説明し、どう補強するか」で面接での印象が大きく変わります。
単に空白を埋めるのではなく、ブランクを経て得た学びや経験を整理し、未来志向で伝えることが重要です。ここでは、履歴書と職務経歴書の具体的な書き方のポイントを紹介します。
履歴書の書き方のポイント
履歴書の職歴欄にブランクがある場合、無理に隠そうとせず、シンプルに記載するのが鉄則です。退職やブランク詳細を長々と書くと「言い訳」に見えてしまうことがあるため、簡潔にとどめましょう。
一方で「資格欄」はブランクを補強する大きな武器になります。ブランク中に取り組んだ資格取得や学習成果を記載することで、「空白ではなく成長の時間だった」と印象づけられます。たとえば「AWS認定資格取得」「基本情報技術者試験合格」といった形で明確に書くことで、学びの姿勢とスキルの裏付けを示せます。
さらに「志望動機」欄は未来志向で仕上げることが大切です。「学び直しを通じて得たスキルを貴社で活かしたい」「ブランクを経て改めてエンジニアとしての道を歩む、決意を固めた」といった表現を盛り込みましょう。これにより、ブランクがマイナスではなく「再スタートの準備期間」として伝わりやすくなります。
職務経歴書の書き方ポイント
職務経歴書は、履歴書よりもさらに具体的に「ブランクの扱い方」が問われる書類です。職歴欄と同様に、ブランクの理由は、あくまで簡潔に一文でまとめましょう。「介護のため」「療養のため」「育児のため」など、事実だけを短く記載すれば十分です。
採用担当者が知りたいのは理由そのものではなく、「その後、どのようにスキルを維持・向上させたか」です。したがって、ブランク期間に取り組んだことを具体的に書くことが肝心です。
例えば、以下のような活動は大きな評価ポイントになります。
- プログラミングスクール受講(例:Java、Python、AWSなど)
- 資格取得(AWS認定資格、基本情報技術者試験など)
- 個人開発プロジェクト(GitHubにコード公開)
- オープンソースへのコントリビュート(Pull RequestやIssue対応)
- 技術書や勉強会への参加(参加回数や学んだテーマを明記)
これらを記載する際には、シンプルに「勉強しました」では熱意や取り組みの内容が伝わらないため、成果物や実績を具体的に書きましょう。
例えば「Javaを学習し、Webアプリケーションを個人開発。GitHubに公開し、レビューを受けながら改良を続けた」「AWS認定資格を取得し、クラウド設計の基礎を習得」など、事実や数字を伴う表現に変えることが重要です。
また、実務を意識した表現にすることも評価を高めるポイントです。「独学で勉強」ではなく「○○を開発し、△△の機能を実装。ユーザーからのフィードバックをもとに改修」といった具体的なプロセスを書くことで、採用担当者は「この人は実際の業務に近い経験を積んでいる」と感じやすくなります。
書き方の失敗例/成功例
これまで解説してきたようにブランクをどう表現するかで、採用担当者の受け止め方は大きく変わります。ここでは、よくある失敗例と成功例を比較してみましょう。
<失敗例>
| 2022年4月〜2023年3月 ブランク期間 特に就業はしていませんが、独学でプログラミングを学習していました。 |
「何をどのくらい学んだか」「どんな成果があったのか」が曖昧で、学習姿勢は伝わっても評価にはつながりにくい書き方になっています。
<成功例>
| 2022年4月〜2023年3月 キャリアブランク期間 【ブランク期間の活動内容】 ・UdemyやProgateを利用し、Java・Spring Bootを体系的に学習 ・ポートフォリオとしてWebアプリ(書籍管理システム)を開発し、GitHubに公開 ・AWS認定クラウドプラクティショナー資格を取得(2023年1月) |
上記のような記載であれば「取り組んだこと+成果物+客観的な証明(資格・GitHub・学習サービス)」がセットになっているため、努力と実績が明確に伝わり、採用担当者も安心できます。
このように、事実を具体的に示す+成果物や資格などの証拠を添えることで、ブランク期間が“弱点”ではなく“学習と成長の時間”として評価されやすくなります。
おすすめ記事:自社開発”や”受託開発”に未経験から行ける?現実的なキャリアルートと戦略を解説
ブランクを強みに変える面接のポイント

書類でブランクの印象をある程度コントロールできても、最終的に評価が決まるのはやはり面接です。
そのためには、ブランクをただの“空白”として語るのではなく「準備期間」「経験の蓄積」として前向きに伝えることが重要です。ここでは、面接でブランクを強みに変えるための具体的なポイントを解説します。
ブランクの理由は短く、前向きに
まず大切なのは、ブランクの理由を長々と話さないことです。「介護をしていたため退職しました」「療養のため一定期間休んでいました」と簡潔に述べるだけで良いでしょう。詳しく語りすぎるとどうしても言い訳がましく聞こえ、採用担当者の心証が悪化してしまう可能性があります。
むしろ大事なのは、そのブランクをどう前向きに捉えてきたかです。たとえば「この期間を通してキャリアを見直し、エンジニアとして専門性を高める決意を固めました」と伝えれば、「停滞」ではなく「準備期間」として印象づけられます。ブランクはネガティブに語るのではなく、未来への助走期間としましょう。
ブランク中の成果物を示す
面接では「ブランク中に何をしてきたか」を具体的に語ることが重要です。特にエンジニアの場合、学習や活動の成果が可視化されていると強力なアピール材料になります。
- 資格取得:「AWS認定ソリューションアーキテクトを取得しました。クラウド設計の基礎を体系的に学べたと実感しています」
- 個人開発:「ReactとSpring Bootを使い、勤怠管理アプリを開発しました。コードはGitHubで公開しており、レビューを受けながら改善を進めています」
このように、具体的な取り組みと成果物を添えて話せば、採用担当者も「ブランク中も実際に行動してきたのだな」と納得できます。ポイントは「勉強しました」で終わらせず、「何を学び、どのような形で成果を残したか」を示すことです。

今後のキャリア意識とやる気をアピール
企業が最も重視しているのは「入社後にどう活躍してくれるか」です。したがって面接では、ブランク中の行動を未来のキャリアにどう結びつけるかをしっかり伝えましょう。
NGな答え方の典型は「正社員として安定して働きたい」というもの。これは自己都合に聞こえ、企業への貢献が見えません。代わりに、次のように語ると効果的です。
- OK例:「クラウド環境を活かした開発経験を積み、貴社のDX推進プロジェクトに貢献したいと考えています」
- OK例:「これまでの学習で得たスキルを基盤に、チームでの開発経験を積みながら中長期的にバックエンド領域を強化していきたいです」
このように、自分の目標と企業の方向性を重ね合わせて語ることで、「即戦力としてのポテンシャルがある」と判断されやすくなります。
面接でブランクを強みに変えるには、①理由を短く前向きに伝える、②成果物を具体的に示す、③今後のキャリア意識を明確にする、という3つのポイントが欠かせません。
言い訳ではなく「この期間をどう活かしたか」、そして「これからどう貢献できるか」を語ることができる人材は、ブランクがあってもむしろ信頼を得やすいのです。ブランクを恥じる必要はありません。自分なりの経験と努力を、堂々と面接の場でアピールしましょう。
ブランクがある人におすすめの転職の進め方
これまで解説してきたようにブランクがあっても、伝え方ひとつで印象は大きく変わります。書類ではブランク中に得た経験や学びを整理し、面接では「今後どう活かすか」を前向きに語ることで、不安材料をむしろ強みに変えることができます。
ただし、自分だけでこうした転職戦略を立てるのは難しいもの。そんなときは、エンジニア専門の転職エージェント「Unitas(ユニタス)」に相談するのがおすすめです。経験豊富なキャリアアドバイザーが一緒に「企業にどう説明すべきか」を考え、推薦状でブランクの背景をフォローしてくれます。
「ブランクは過去、転職は未来」。視点を切り替えて、次のキャリアを切り開きましょう。
📩キャリアの悩み、Unitas公式LINEで気軽に相談できます!
▶︎ https://lin.ee/8OARMOS
Unitas (ユニタス)転職アドバイザー 菅原 康平(すがわら こうへい)
宮城県出身。大学卒業後、通信業界で営業としてキャリアをスタートし、4年間勤務。
その後、Recruit(リクルート)に転職し、Hotpepperグルメ領域で法人向け営業を担当。
顧客の課題に向き合い、ソリューション提案を重ねる中で「企業と人をつなぐ仕事」に可能性を感じ、Unitasに参画。
現在は転職アドバイザーとして、ブランクを抱える方や未経験からの挑戦者を中心に、転職の伴走支援を行っている。