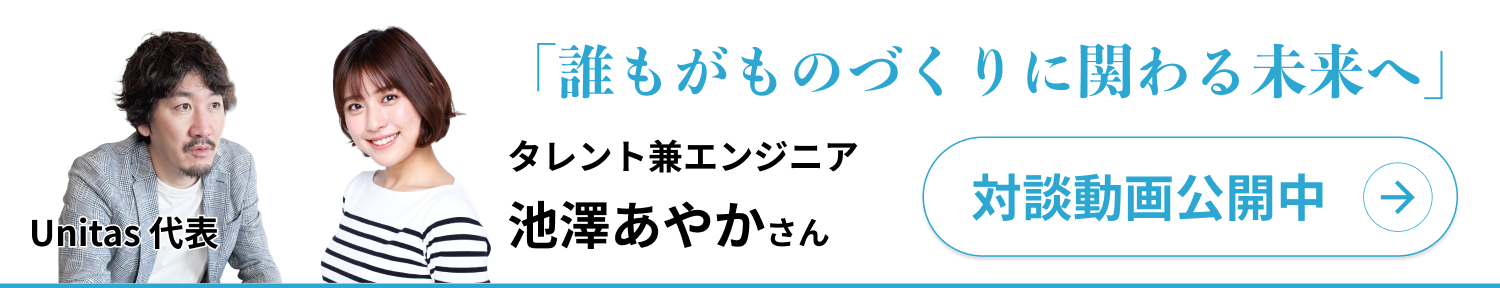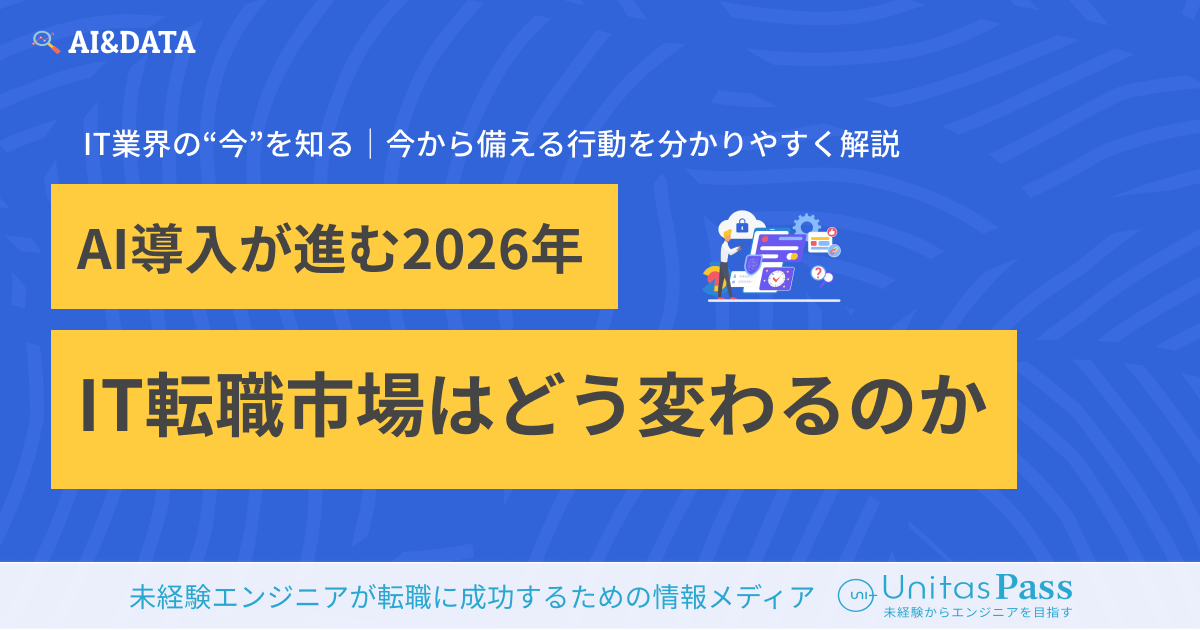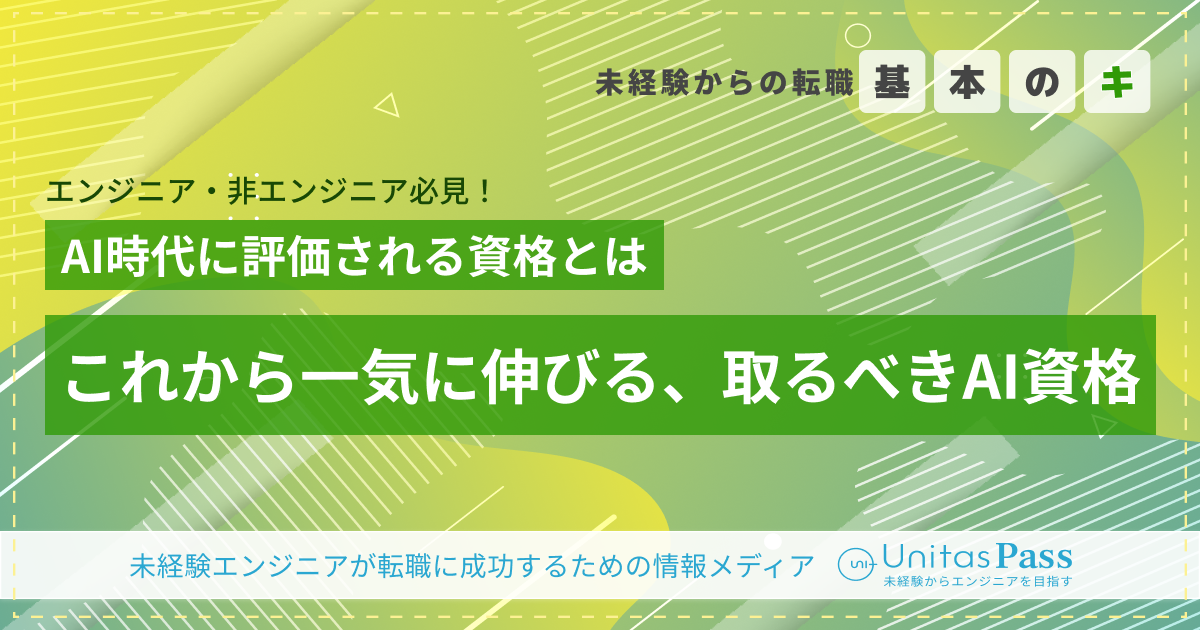最低給与が1,000万円?エンジニア給与相場はどこまで上がるのか
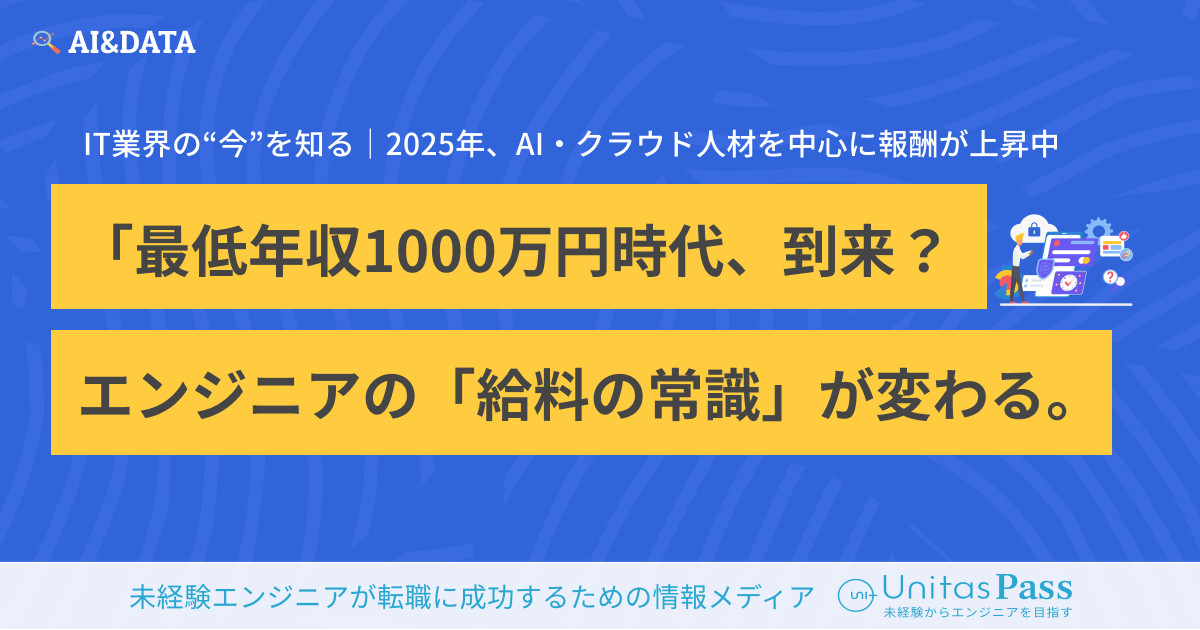
「最低年収1,000万円」──2025年、さくらインターネットの採用ニュースが話題になりました。
けれど、“そんなの一部の天才だけの話でしょ?”と思う人も多いはず。
実は今、国内でもエンジニア給与の“基準”そのものが変わり始めています。
この記事では、給与相場の上昇トレンドと、これからキャリアを築く人が押さえるべきポイントを解説します。
さくらインターネットは年収2,000万円超エンジニアを採用中

2025年1月にインターネットインフラサービスを提供するさくらインターネットが、高度人材の採用を進めている旨が報道されました。同社はGPUクラウドとガバメントクラウドという国家的にも重要なプロジェクトを同時進行で進めています。
参考:GPUとガバクラで目指す「国産クラウド最強」、さくらインターネットの野望 | 日経クロステック(xTECH)
その実現には、AWSやGoogle Cloudと肩を並べるような性能を実現する高度な開発力が不可欠であり、外資系ITやメガベンチャーで活躍するトップ人材を採用するため、1,000万円台後半から2,000万円超という報酬を提示しているとのことでした。同社の平均給与が600万円台であることを考えると、従来の水準から乖離していることになります。
報道の中では、「600万円で優秀なエンジニアが来るかというと、来ない。やはり最低、現場レベルでも1000万円からというレベルになる」という同社の田中邦裕社長のコメントも紹介されています。このことは、優秀なエンジニアは世界的に不足しており、日本企業が本気で競争に挑むためには、従来の「600万〜800万円程度」という給与相場では到底太刀打ちできないことを示しています。
さくらインターネットの事例は、国内のエンジニア求人市場全体に「優秀な人材を確保するには最低でも1,000万円」という新たな基準を示すことになりました。結果として、給与水準の底上げが進めば、エンジニアの給与相場の常識が大きく変化する可能性もあります。
日本と世界の“年収格差”はどれくらい?
近年、「600万円前後」の年収では、優秀なエンジニアを確保することが難しくなっています。その背景には、DX推進やAI活用の急速な広がりによる人材需要の高まりがあります。高度なスキルを持つエンジニアは世界中で引く手あまたとなり、需給バランスが大きく崩れているのです。
さらに、日本国内と海外・外資系企業との給与格差も要因の一つと考えられます。外資系や国内のメガベンチャーでは、若手でも1,000万円を超える待遇が珍しくなく、グローバル企業ではそれ以上の報酬が一般的です。
例えば、人材サービス企業が2022年に行った調査によると、ソフトウェア開発者の給与額ランキングで1位はスイス、2位はアメリカで、日本は20位にとどまっています。また、別の調査によると日本在住の英語を話すソフトウェア開発者の年収中央値は950万円と報告されており、既に“世界標準”から見れば1,000万円に近い水準が当たり前となりつつあります。
参考:世界のIT技術者、給与額1位はスイス、2位はアメリカ。日本は20位に留まる|CodeZine(コードジン)
なぜ日本だけ給与上昇が遅れているのか
このように「グローバル基準」と「日本の平均年収」の間には大きなギャップが存在します。日本のITエンジニアの平均年収はおよそ450万円程度であり、その水準を基準に「600万円なら十分だろう」と考える企業も少なくありません。
しかし、グローバルに企業を選ぶことができるエンジニアにとっては、その給与額は自身の市場価値の象徴であり、キャリア選択の重要な判断材料となります。結果として、日本企業が提示する従来の給与レンジでは、国際競争力を持つ人材を引き寄せることができなくなっていると考えられます。
「600万円で優秀な人材を採用できる時代は終わった」と考えなければ、日本の企業はDXやAI技術の発展の波に取り残されてしまうかもしれません。
これからのエンジニアは最低年収が1,000万円に?

これまで解説してきたようにエンジニアの給与相場は、近年大きな転換点を迎えています。
エンジニア向けの転職サービスが公開した調査によれば、2020年から2024年にかけて平均提示年収は644万円から791万円へと上昇し、中央値も2024年12月には800万円に到達しています。特に注目すべきは1,000万円レンジの拡大で、提示割合は0.7%から8.4%へと増加。従来は一部の外資や経営層に限られていた水準が、国内市場でも現実的なラインになりつつあるのです。
参考:【転職ドラフト調査】ITエンジニアへの平均提示年収は5年間で147万円増。800万円以上の年収提示割合は4割を占め、5年前の約2.6倍に | 株式会社リブセンスのプレスリリース
この背景には、AIやクラウド技術の発展に伴い、企業のDXをけん引できる人材の需要が急増していることがあります。プログラミングスキルだけでは差別化が難しくなり、事業課題を理解して解決に導ける力や、チームをまとめるリーダーシップが高く評価されるようになってきています。
例えば、C++やScalaといった難易度の高い言語、SwiftやKotlinなどアプリ開発分野のスキル、さらにはエンジニアリングマネージャーの経験を持つ人材には、1,000万円を超える年収が提示されるようになってきています。
つまり「年収1,000万円」はもはや一部の特別な人の到達点ではなく、優秀なエンジニアにとっての“スタートライン”になりつつあるのです。これは単に報酬が上がるという話にとどまりません。エンジニアの役割が「コードを書く人」から「事業を動かす中心人材」へとシフトしている証拠でもあります。
今後、給与の二極化が進み、課題解決力やマネジメント力を備えた人材はグローバル基準で評価され、最低年収1,000万円が現実的な基準となっていく可能性もあります。
どのようなエンジニアが年収1,000万円を達成するのか

「エンジニア=年収600万円前後」という常識は崩れつつあり、年収1,000万円を超えるエンジニアも増えていますが、その条件は単なるプログラミング能力の高さにとどまりません。ここでは、具体的にどのようなエンジニアが高収入を実現しているのか、を解説します。
年収1,000万円を実現するために求められるスキル
まず重要になるのは、社会的需要の高い領域のスキルです。AIやデータサイエンスはもちろん、クラウドアーキテクチャやセキュリティ領域の知見は、DX推進やAI導入を急ぐ企業にとって欠かせません。
これらのスキルを持つエンジニアは、事業の根幹を支える存在となり、企業が高額の報酬を提示する大きな理由となっています。
年収1,000万円を実現するために求められる能力
エンジニアスキルに加えて、ビジネスマンとしての「能力」も重要になります。ビジネス視点を持ち、開発を経営課題の解決につなげることができれば、良い待遇で企業に迎えられる可能性が高まります。
さらにチームを牽引するマネジメント力や、海外企業との協業を前提としたグローバル対応力があれば評価されやすいでしょう。単なる“つくる人”から“事業を動かす人”へと役割を広げられるかが、年収1,000万円の壁を超えるカギなのです。
エンジニアで年収1,000万円を実現した事例
実際にエンジニアとして年収1,000万を実現できる職種・ポジションの事例としては、スタートアップや大手企業で技術戦略を担うCTO、難易度の高いプロジェクトを支えるシニアエンジニアが挙げられます。
また、近年はフリーランスでも高単価案件を獲得し、年収1,000万円を超える例が増えています。特にクラウドやAI関連の案件では、月100万円を超える報酬が珍しくなく、自由な働き方と高収入を両立するエンジニアも出てきています。
このように、年収1,000万円を達成するエンジニアとは、特定技術に強みを持ちつつ、それをビジネスや組織に結びつけられる人材だと考えられます。これからのキャリアを考える上で、技術力だけでなく課題解決力やマネジメント力を磨くことが、次世代のエンジニア像、ひいては年収増につながっていくでしょう。
エンジニアの今後の給与動向と「二極化」の未来

エンジニアの給与相場が上昇していく一方で、今後は「二極化」も進行していくと考えられます。エンジニア個人と企業、それぞれの立場から今後の給与の動向について解説していきます。
AIが中間層を“押し下げる”構造
これまで解説してきたようにすでに一部の上位層は年収1,000万円を超え、グローバル市場で通用する人材として高額のオファーを受けています。一方で、中間層の給与は依然として大きな上昇が見込めず横ばい傾向が続く可能性があります。
さらに、単純なコーディングや保守業務を中心とした下位層は、AIや自動化ツールの発展によって淘汰されるリスクすら抱えています。まさに「スキルと役割による明暗」がこれまで以上に鮮明になる時代が訪れようとしています。
成果主義の波が日本企業にも到来
こうした流れの中で、日本企業は従来の年功序列や一律的な給与制度を見直す必要に迫られています。グローバル基準で競争できる人材を確保するためには、実力や成果に応じた報酬体系を整備しなければなりません。
特に、AIやクラウド、セキュリティといった戦略領域を担える人材を引き止めるためには、1,000万円以上の提示を前提とした報酬設計が不可欠です。給与水準を国際競争力のある水準へと引き上げられるかどうかが、日本企業の将来を左右する分岐点となるでしょう。
給与だけではなく「働きがい」で差別化する企業も
ただし、給与だけで差別化することには限界があります。そのため、企業にとってはリモートワークやフレックス制度、明確なキャリアパス、挑戦的なプロジェクトへの参画機会といった「働きがい」を提供することが、優秀人材を引きつける大きな要素となります。
給与が大きく変わらなければ「やりがい」や「働く環境」によってエンジニアに選んでもらうこともできるでしょう。
今後のエンジニア市場は、給与の二極化と同時に、企業の人材戦略そのものが問われる時代へとなっています。給与と働きがいという二つの視点で採用に取り組むことができる企業が熾烈な人材獲得競争を勝ち抜いていくことになるでしょう。
若手・未経験エンジニアが今からできること

エンジニアの給与相場が急速に上がる一方で、若手や未経験者がいきなり年収1,000万円に到達するのは容易ではありません。しかし、将来的に高収入を実現できる可能性を高めるために、今から取り組めることは数多くあります。
需要が高いスキルを習得する
まず重要なのは、高需要分野のスキルを習得することです。Pythonを使ったデータ分析やAI開発はもちろん、AWSやGCPといったクラウドサービス関連の資格取得なども、キャリアの土台として高い評価を受けます。
これらは今後も需要が拡大し続ける分野であり、未経験からでも学習を始める価値があります。
語学能力の向上で外資・グローバル案件を視野に
エンジニアスキルに加えて、英語力の習得も欠かせません。技術ドキュメントの多くは英語で公開されており、外資系企業やグローバル案件を視野に入れる上で英語は必須スキルです。
英語を武器にできれば、選択肢は国内だけでなく世界へと広がり、より高い報酬を得られるチャンスが増えます。
適切なキャリア戦略の策定が必要
さらに、キャリア戦略を早期に描くことも重要です。場当たり的にスキルを積み上げるのではなく、「自分はAI分野で専門性を深めるのか」「クラウド基盤の設計に強みを持つのか」といった方向性を明確にすることで、学習や経験の積み方が効率的になり、数年後の市場価値が大きく変わります。
若手や未経験だからこそ、今から正しい分野に投資し、戦略的にキャリアを積み上げることが、未来の高収入につながる第一歩となるのです。

Unitas(ユニタス)を活用して「1,000万プレイヤー」を目指すキャリア戦略を

「年収600万円では優秀人材が来ない」という事実は、日本のIT人材市場が大きな転換期にあることを示しています。AIやクラウドなど成長分野のスキルに加え、ビジネス視点やマネジメント力を磨くことで、年収1,000万円を超えるキャリアは十分に射程圏内です。
こうした状況下で重要になるのは、いまから自分のキャリアをどうデザインするか、を明確にしておくことです。もし「何を学ぶべきか」「どう動けばよいか」に不安があるなら、未経験からのエンジニア転職を支援してきた Unitas(ユニタス) に相談してみてください。
キャリア戦略からスキル習得、転職サポートまで伴走してくれる存在は、1,000万プレイヤーを目指すパートナーとして最適といえるでしょう。
これからのエンジニア市場では、“待つ人”より“動く人”が強い時代。
Unitasでは、AI・クラウド・データなど将来性の高い分野でのキャリア設計を、あなたと一緒に考えます。
「将来いくら稼げるようになりたいか」から逆算したキャリア戦略、無料で相談できます。