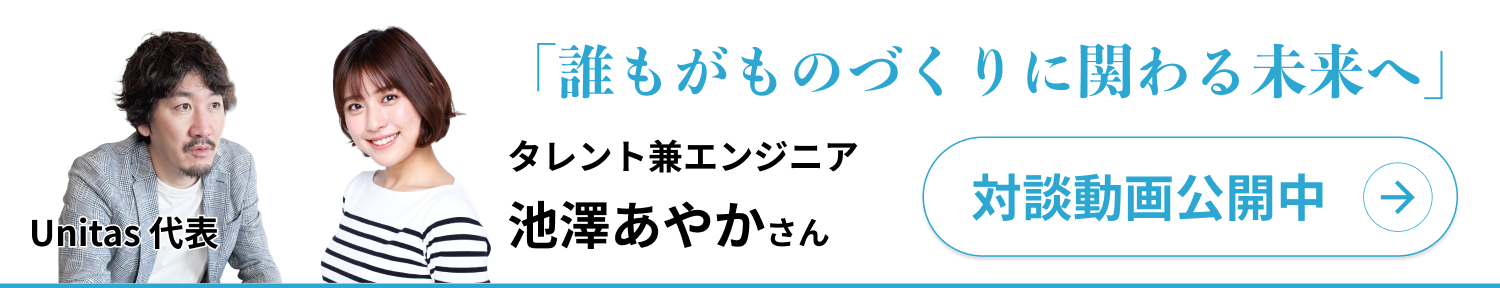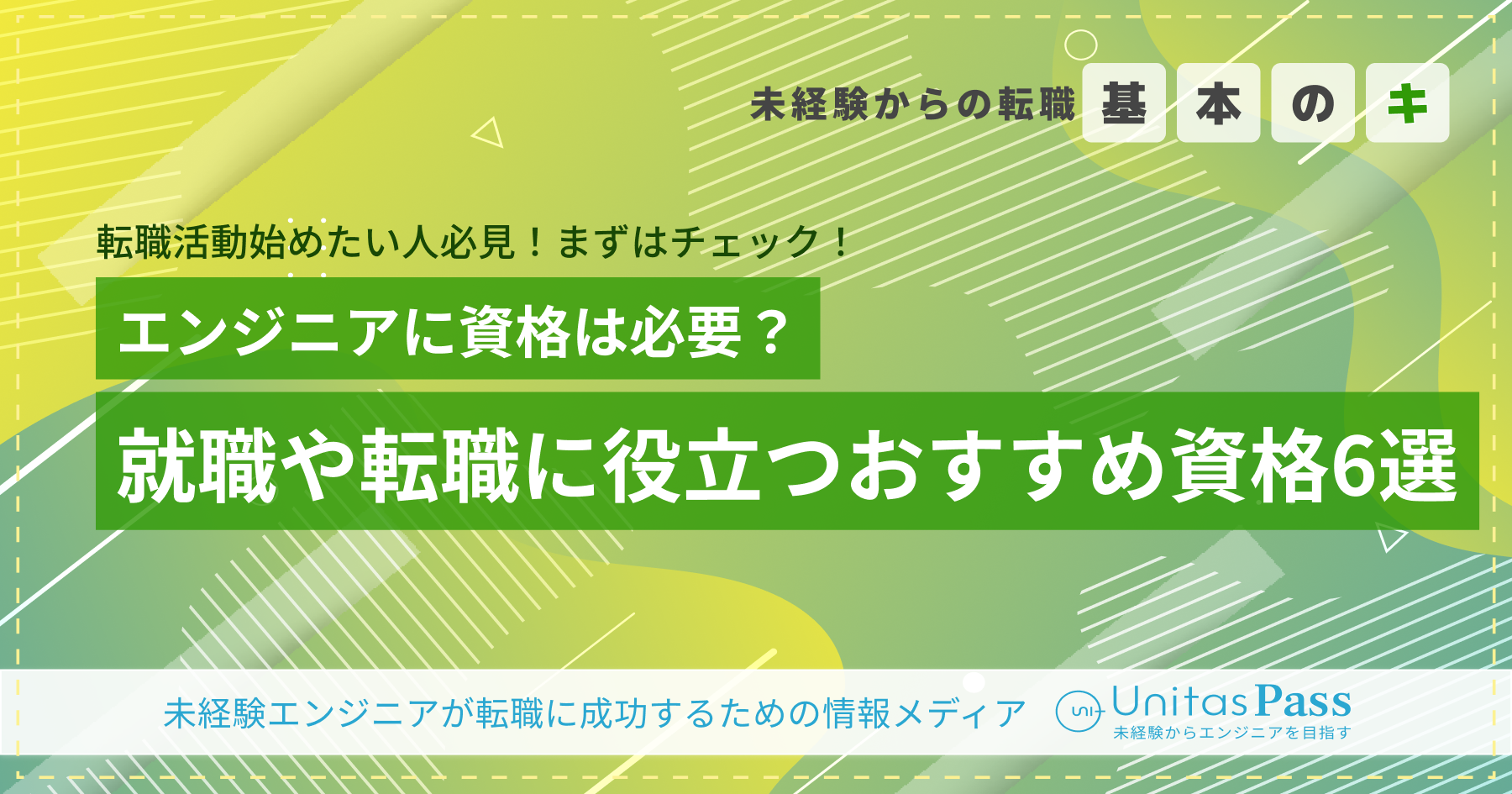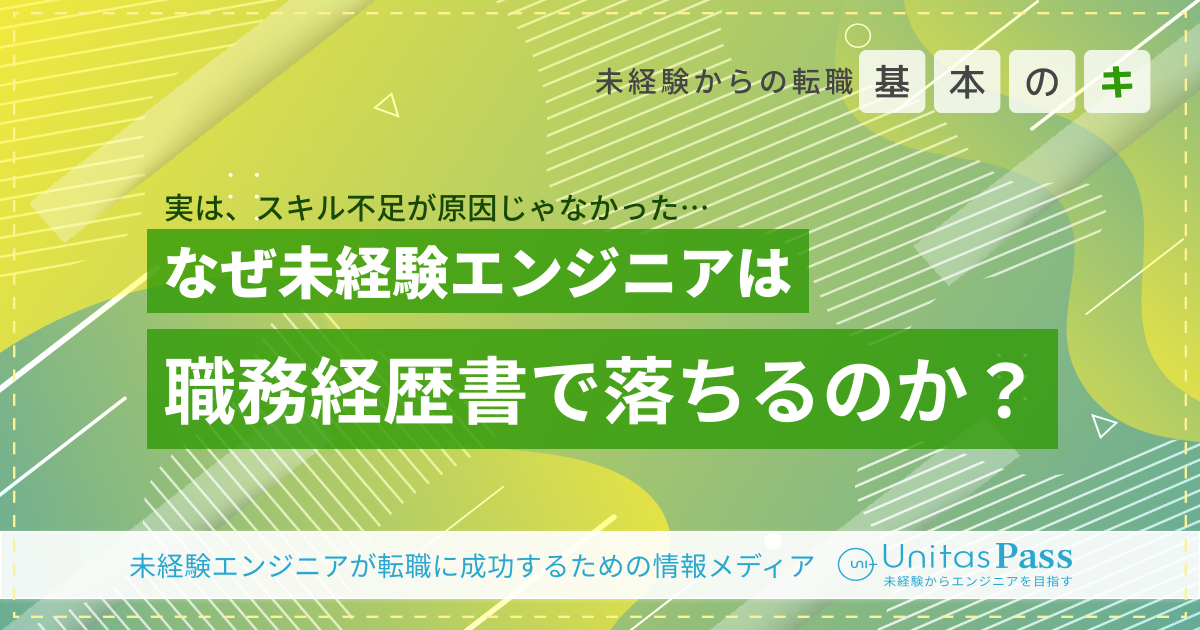エンジニアの年収が低い人の共通点とは?稼げる人との違いとキャリア戦略を解説
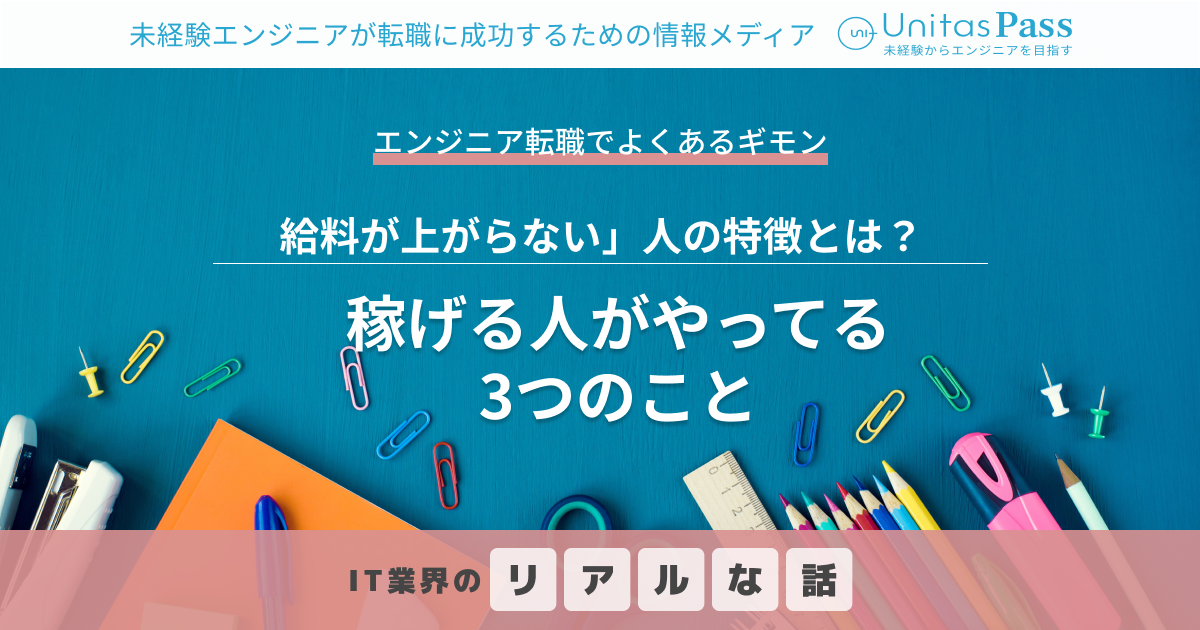
「エンジニアになれば年収が上がるはず」。そんな期待を胸に転職したものの、「思ったより稼げない」と感じている人は少なくありません。実際、同じ職種でも年収には大きな差が出るのが現実です。
そこでこの記事では、エンジニアの給料事情を紐解きながら、年収が低い人・高い人の違いや転職時に意識すべきポイントを解説。年収アップを実現するためのモデルキャリアも紹介します。
エンジニアの給料は本当に低いのか?

ITエンジニア全体の平均年収は、およそ450〜550万円といわれており、民間企業の平均年収460万円(国税庁|令和5年分民間給与実態統計調査結果を参考)と比較すると高めの水準といえます。
しかし実際の年収は、職種や働き方によって大きな開きがあります。厚生労働省 「IT・デジタル人材の労働市場に関する 研究調査事業」 調査報告書の職種別・ITスキルレベル別の賃金相場によると、スキルレベルの高いエンジニアは実務未経験者や初級レベルのエンジニアに比べておよそ1.5倍の年収を得ていることが明らかになりました。
また、同じスキルレベルでも業務内容によって賃金水準に差があり、「企画・プロジェクト管理」>「運用・保守」>「設計・構築」 の順で年収が高い傾向があります。
<職種別・ITスキルレベル別の賃金相場>
出典:厚生労働省 「IT・デジタル人材の労働市場に関する 研究調査事業」 調査報告書
(参考)スキルレベル
出典:厚生労働省 「IT・デジタル人材の労働市場に関する 研究調査事業」 調査報告書
ここからは、年収を左右する「エンジニアの特徴」を探っていきます。
年収が低いエンジニアの特徴とは?

「稼げるエンジニア」を目指すために、まずは年収が低いエンジニアにどんな特徴があるのか見ていきましょう。
スキルの汎用性が低い
年収が低いエンジニアの特徴のひとつは、「スキルの汎用性の低さ」です。特定の業務システムや独自仕様の社内システムの開発経験が中心だと、経験を他の企業で再利用しにくく転職市場での評価が低くなりがちです。
また、スキルの将来性も年収に直結します。例えば、自動化の影響を受けやすいマークアップ中心のコーダー職は年収250〜400万円にとどまることが多いです。
下請けや受託での単価の限界
下請けや受託は発注単価が決まっていることから、スキルが高いエンジニアでも報酬に反映されにくいのが現状です。
また、受託開発やSES(客先常駐)は発注単価から「元請け」「仲介企業」「自社」と中間マージンが差し引かれます。そのためエンジニア自身に入る報酬はかなり少なくなり、年収300〜450万円程度で伸び悩むケースが多いです。
「言われたことだけやる」受け身のスタイル
年収が上がりにくいエンジニアの中には、「受け身の姿勢」が習慣化している人も多く見られます。上司やクライアントからの指示をそのまま実行するだけで課題発見や改善提案などの能動的な働きかけがない場合、組織内での評価が上がらず、結果的に年収にも反映されません。
また、こうした受け身のスタイルでは「上流工程」や「技術選定」「業務改善」といった価値の高いフェーズに関与する機会が減ってしまいます。その結果、スキルや経験の幅が広がらずキャリアアップにもつながりにくいため、年収も増えづらい傾向にあります。

年収が高いエンジニアの特徴とは?

次に、「稼げるエンジニア」が持っている視点やスキルセットについて見ていきましょう。
技術力+αの武器を持っている
年収が高いエンジニアは、コードが書けるだけではなく設計の意図を汲み取って改善や最適化の提案ができるなど、純粋な技術力に加えて「+αの価値」を提供できる人が多いです。
例えば、「ユーザー体験を高めるためにはどんなUIが必要か?」という観点から設計を考えられるエンジニアは、プロダクト価値の向上に直接貢献できる存在です。こうした人材はマネージャーやリードポジションにも起用されやすく、年収1,000万円超えも不可能ではありません。
市場価値の高い分野に身を置いている
「成長している分野」や「企業ニーズが高まっている技術領域」は報酬も高めです。特に近年は、クラウド(AWS、GCP、Azure)やセキュリティ、データ分析、機械学習といった分野が注目されており、それらに強いエンジニアは市場価値が高く、高単価の案件やオファーが集まりやすい傾向にあります。
さらに、TypeScriptやNext.js、Go、Rustなどのモダンな技術に対応できることも評価につながりやすいため、このような新しい技術に積極的な姿勢も高収入を得るためには重要です。
発信・アウトプットをしている
もうひとつの重要な特徴が、「自分の技術や経験を発信していること」です。技術ブログの執筆やカンファレンスでの登壇、ポートフォリオの公開などを通じて、自分のスキルや考え方を「見える化」している人は、企業やクライアントから声がかかりやすくなります。特に2025年現在は、X(旧Twitter)やZenn、Qiitaなどでの日常的な発信が「スカウトにつながる名刺代わり」となっており、ポートフォリオ以上に採用担当の目に留まりやすい手段となっています。
これらの活動がきっかけで転職や案件のオファーにつながるケースも珍しくなく、特にフリーランスや副業では案件獲得に直結する武器になります。また、転職市場でも何も発信していない人より定期的に技術ブログを書いている人のほうが注目されやすく、スカウトや選考で有利になる傾向があります。
なお、2025年現在では、GitHub Copilotなどの生成AIによるコーディング支援ツールの普及により、従来の「実装スピード」や「記述量」だけではエンジニアとしての価値を差別化しづらくなっています。
そのため、AIと共存できるスキルセットとして、設計力・構造的思考・要件定義といった“上流視点”を持つことが、より重要視されるようになってきました。
こうした「考える力」や「抽象化のスキル」は、技術選定やアーキテクチャ設計など、年収の高いポジションに直結しやすい領域でもあります。
転職時に給与アップを狙うためのチェックポイント

エンジニアは、ほかの職種に比べて転職で年収アップを狙いやすいといわれています。しかし、実際には「思ったほど増えない」「かえって年収が下がってしまった」というケースも少なくありません。
そこで、「入社後に後悔しない」ための転職先の見極め方を紹介します。
想定年収・給与テーブルを必ず確認する
転職時に提示される年収は、金額だけでなく内訳まで確認することが大切です。たとえば同じ「年収500万円」でも、みなし残業代を含んでいる場合とそうでない場合で手取り金額に大きな差が生じます。
また、賞与の支給回数や実績、昇給のタイミング・幅なども企業によって差があるため、給与テーブルで確認しましょう。求人票や面接などでの確認が難しい場合は、エージェントを通じて情報を得るのもひとつの手です。
技術職に対する評価基準を聞いてみる
一般的にエンジニアの評価は難しいため、評価軸があいまいな企業も少なくありません。しかし、技術力・設計力・提案力などエンジニア特有のスキルが正しく評価される仕組みがないと成果が認識されず、今後のキャリア形成にも関わります。
面接時に「エンジニアに明確な評価制度があるか」「昇給や昇格が決まる基準」などを質問し、評価に対する企業のスタンスを確認しておきましょう。
職種・担当領域が自分の市場価値につながるか
転職後の仕事内容が、自分のスキルアップや市場価値向上につながるかを見極めることも重要です。例えば「仕様通りに実装するだけ」といった業務では、成長機会が限られてしまいます。要件定義や設計、コードレビュー、運用など幅広く携われるかを確認しましょう。
また、扱う技術スタックが古すぎると、今後転職しにくくなるリスクが生じます。さらなるステップアップを望むなら、モダンな開発環境(クラウド、CI/CD、コンテナなど)やアーキテクチャ設計に関われるかも重要です。
業界に特化した転職エージェントを利用する
転職エージェントには、幅広い業界をカバーする「総合型エージェント」と、特定の業界や業種に特化した「専門特化型エージェント」があります。
総合型エージェントには「求人数が多い」「求人が大手からスタートアップ企業まで幅広い」などのメリットがありますが、年収アップを狙うなら、IT業界やエンジニア職に特化したエージェントの活用がおすすめです。
専門特化型エージェントは企業ごとの給与水準や評価制度、技術スタックなどの内情に詳しく、非公開求人も豊富です。また、自分の経験やスキルに対して妥当な年収相場を教えてくれるため、過小評価されずに交渉を進められるのもメリットです。
年収アップを実現したエンジニアのモデルキャリア

年収アップを目指すには、目の前の業務をこなすだけでなく「将来どうなりたいか」を意識することが大切です。そこで、未経験からスタートして年収アップを実現した2つのリアルなキャリアパターンを紹介します。
モデル①:フロントエンド→フルスタックへ進化したWeb系エンジニアAさんの場合

【1年目】未経験でフロントエンドエンジニアとして入社(年収350万円)
HTML/CSS/JavaScriptを使ったフロントエンドの業務をおこなう。
【2年目】フルスタックエンジニアとして活躍の幅を広げる(年収450万円)
実務経験を積みながら、Node.jsやExpress、データベース、API設計といったバックエンド領域にも挑戦する。
【3年目】チームの中心メンバーとして活躍(年収600万円)
コードを書くことに加え、設計・レビュー・改善提案も担うようになり、チームの中心メンバーとして活躍する。
【5年目】テックリードとしてチームを牽引する存在に(年収700万円)
テックリードに抜擢され、プロダクト全体の技術方針にも関与する。
Aさんは、ReactやNext.js、TypeScriptなどモダン技術も積極的に取り入れています。また、社外発信や継続的な学習にも取り組んでいることから転職市場で評価も高く、今後はマネジメントやプロダクトマネジメントなどより上流のポジションへの展開も視野に入れています。
モデル②:社内SE→クラウドエンジニア→SREへ成長したインフラ系エンジニアBさんの場合
【1年目】未経験で社内SEとして入社(年収380万円)
オンプレミス環境の保守・運用業務を担当。Linuxの基礎やシェルスクリプトを活用した自動化にも取り組み、インフラの土台を学ぶ。
【2年目】クラウドエンジニアとしてスキルの幅を拡大(年収500万円)
AWSやGCPといったクラウドサービスの導入・移行を経験。クラウドの基礎設計やセキュリティにも関わるようになり、インフラの知識を体系的に深める。
【3年目】最新技術を取り入れた自動化・運用改善を実践(年収650万円)
TerraformやAnsibleによる構成管理、CI/CDパイプラインの構築など、インフラのコード化(IaC)を推進。業務効率化や安定運用に大きく貢献する。
【5年目】SREとして信頼性・パフォーマンスの要に(年収800万円)
SRE(Site Reliability Engineer)として、監視体制の強化やシステムの可用性向上、トラブルシューティングに注力する。
Bさんは、改善提案やパフォーマンス最適化を通じて組織に不可欠な存在となり、 将来的にはCTO(最高技術責任者)候補としてのキャリアも期待されています。
年収アップのために今からできること

日々の取り組み次第で将来の年収は大きく変わります。スキルの選び方や思考の広げ方、情報収集の仕方などを紹介しますので、今すぐできることから始めていきましょう。
「単価の高い技術」にアンテナを張る
エンジニアとして収入を伸ばすには、需要が高く、単価が高い技術を選んでスキルを磨くことが重要です。日頃からトレンドをチェックし、自分のスキルと照らし合わせて学ぶテーマを選びましょう。
たとえば、クラウド(AWS、GCP)、コンテナ(Docker、Kubernetes)、モダンフロントエンド(React、Next.js)、AI/データ系技術などは、いずれも市場価値が高く評価されやすい領域です。このような需要がある技術を選ぶことで、市場価値と収入が比例しやすくなります。
開発以外の視点を育てる
評価アップを目指すなら、「動けばOK」ではなくユーザー体験(UX)、パフォーマンス、メンテナンス性、セキュリティといった視点を意識しましょう。単なる実装担当からプロダクト全体に貢献できる人材へと進化することで、より高い年収レンジで評価されやすくなります。
また、ビジネスとのつながりを理解することで上流工程にも携われるようになり、キャリアアップへの道が開けます。
自分の市場価値を定期的に確認する
自分の市場価値の把握には、スカウト型転職サービスの利用がおすすめです。届いたオファーを見ることで、自分のスキルがどのくらいの年収で評価されているかが分かり、キャリアの方向性を見直すヒントにもつながります。
また、定期的にスキルや経験を棚卸しすることで、「足りない部分」や「強み」が明確になります。そのギャップを意識して学習や経験を積み重ねていくことで、キャリアや収入の上昇を目指せます。
アウトプットと継続学習の習慣化
技術力は「持っている」だけでは伝わらないため、学んだことや取り組みをブログやQiita、Zennなどで発信することも大切です。自分の専門性を外部にアピールできるだけでなく、発信を通じて知識の定着やフィードバックも得られます。
さらに、アウトプットを継続することで企業からの信頼や注目も集まり、より好条件のオファーを得るきっかけになる可能性もあります。
未経験エンジニアの転職ならUnitas(ユニタス)
エンジニア特化型の人材紹介事業をおこなうUnitasは、未経験からエンジニアを目指す方々の挑戦を全面的に支援。経験豊富なキャリアアドバイザーが一人ひとりに合った求人を提案するとともに、キャリア診断やリスキリング支援なども実施しています。
さらに、「独学で限界を感じている」「何から始めればいいか分からない」といった方のために、受講料無料の短期集中型プログラミングスクール「UnitasDojo」をスタートしました。オンラインで完結することから全国どこからでも参加可能。現役エンジニアやキャリアアドバイザーが、基礎からしっかりサポートします。
エンジニアへの一歩を踏み出すために、オンラインの無料説明会に参加してみてはいかがでしょうか。
まとめ
エンジニアとして高収入を目指すには、ただ技術を学ぶだけでなく「どの職種を選ぶか」「どの技術に注力するか」を戦略的に考えることが重要です。また、キャリアパスを意識してスキルや経験を得ることも、収入アップへとつながります。
日々の学びや技術発信を続けながら、正しい方向に努力を重ねることで、未経験からでも高年収を実現することは十分可能です。まずは自分の市場価値を確認し、足りないスキルを探すところから始めてみましょう。