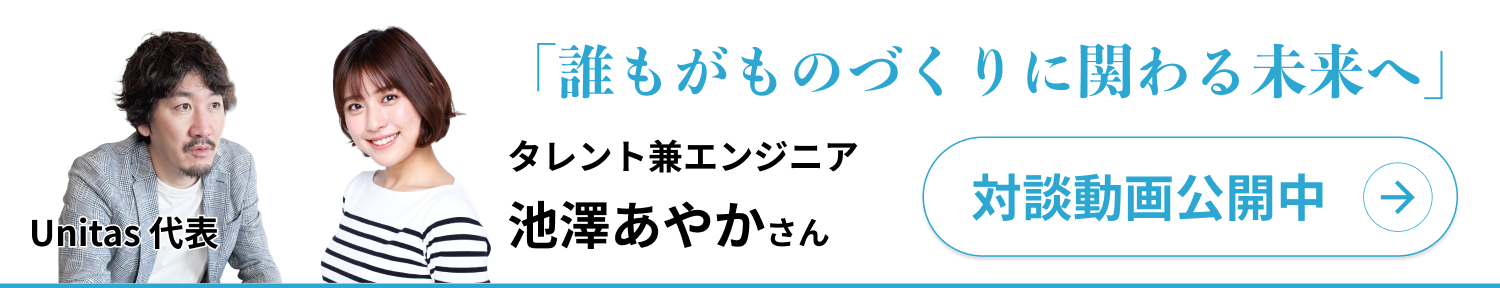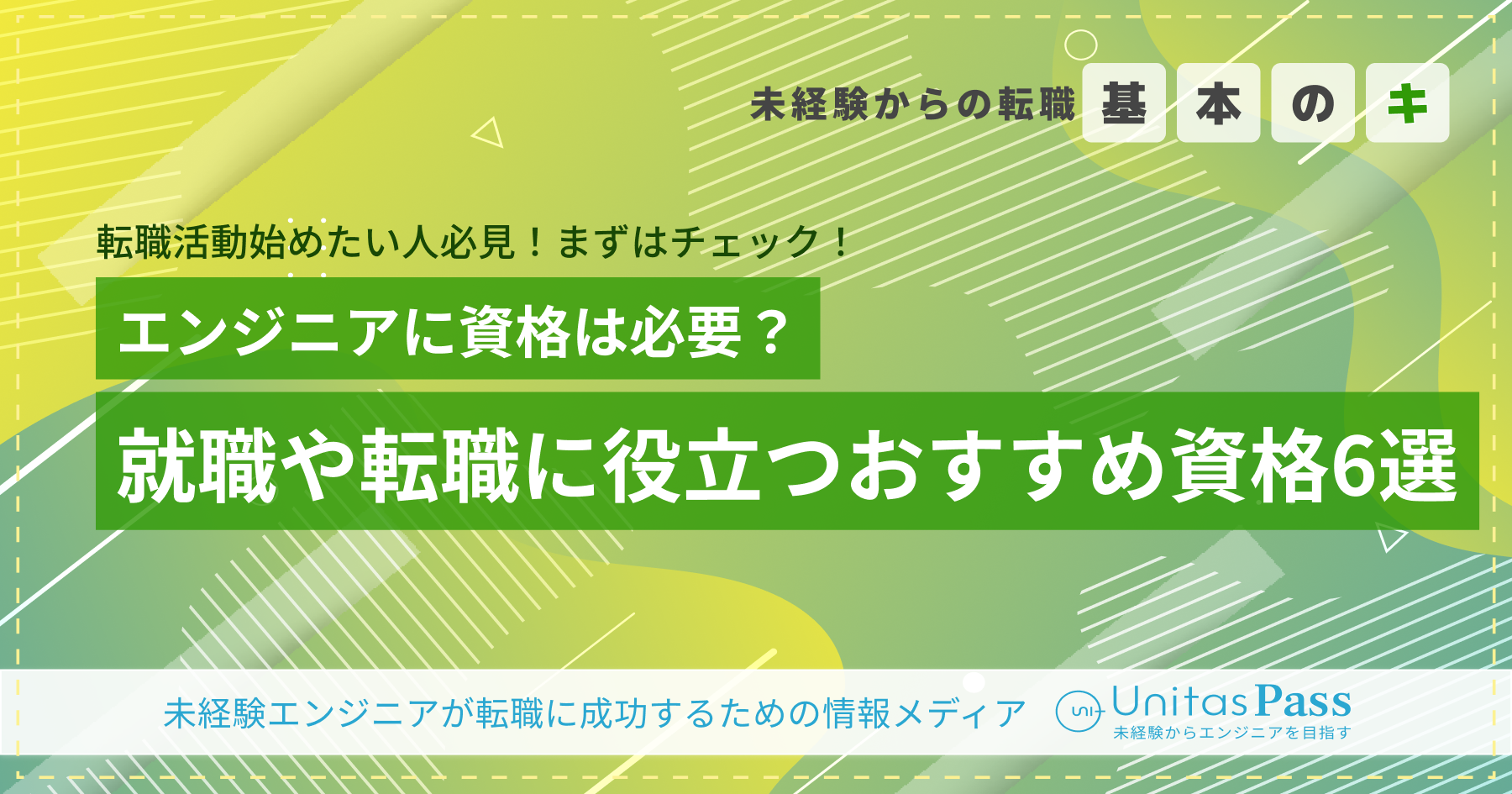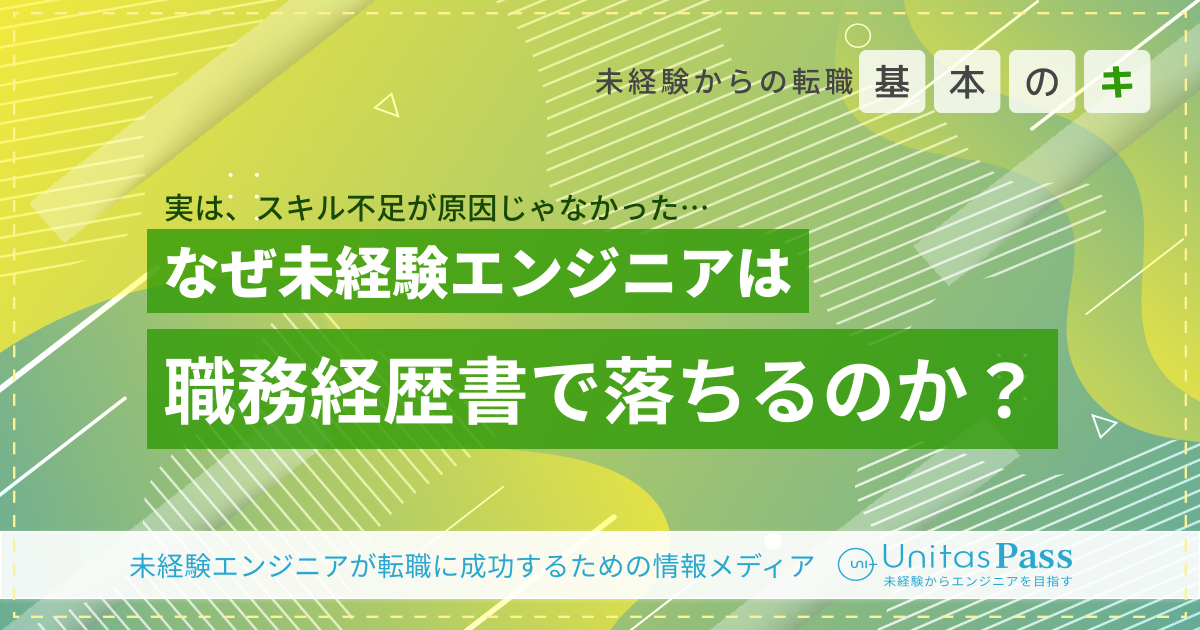未経験エンジニアが入社後につまずく4つの壁とその乗り越え方【後悔しないための準備術】
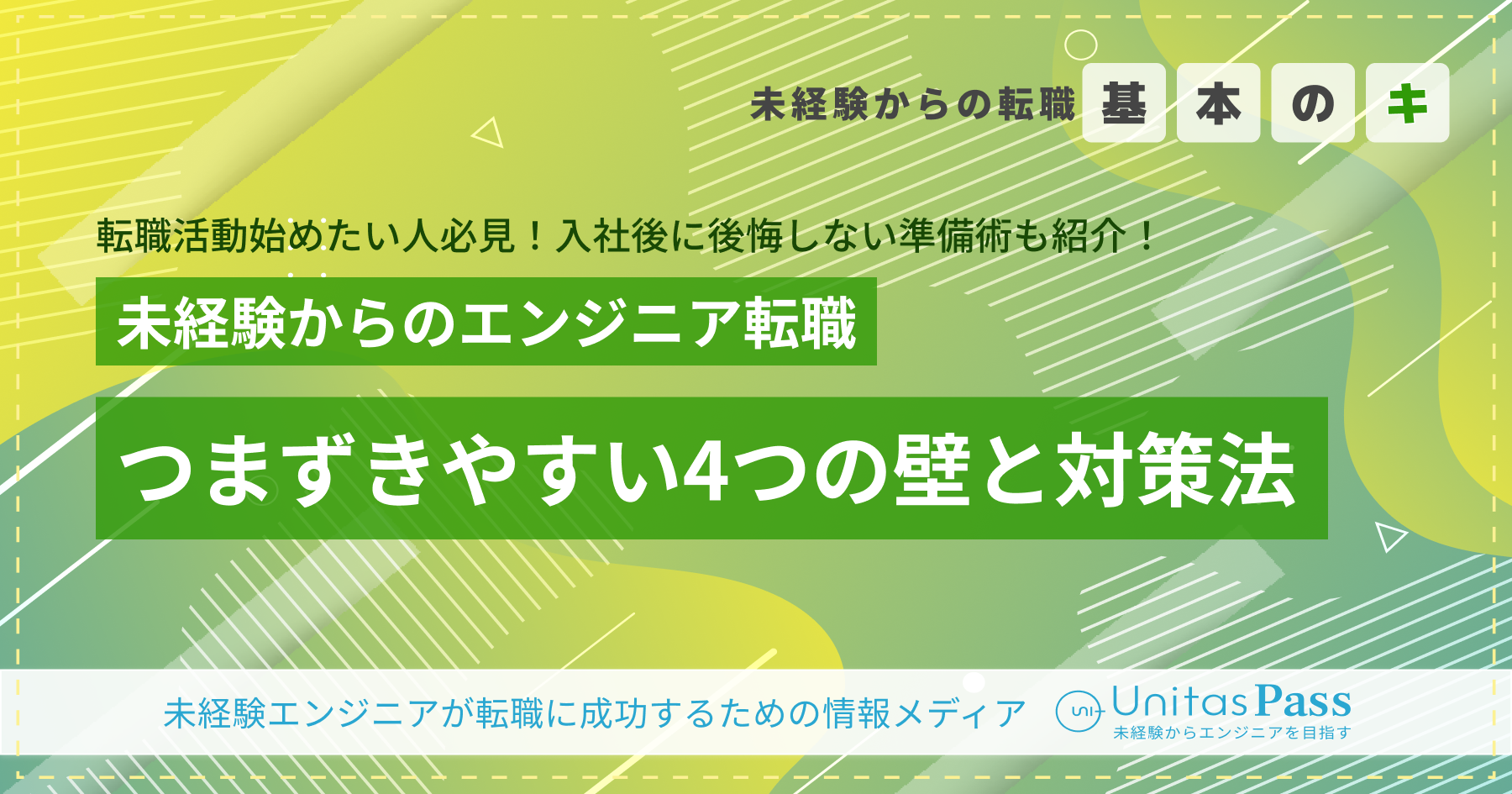
IT業界の人材需要の高まりを背景に、未経験からエンジニアに転職する人が増えています。一方で、無事転職は出来たものの入社後に「思っていたよりも難しい」と感じ、キャッチアップに苦労するケースも少なくありません。
未経験でエンジニアとして働き始めた人は、入社後にさまざまなギャップや課題に直面することがあります。ただし、事前にしっかりと準備をしておくことで、これらの壁を乗り越え、スムーズに現場に順応しながらキャリアを切り拓いていくことが可能です。
この記事では、未経験エンジニアが入社後に直面しがちな現実と課題、そして、その乗り越え方を詳しく解説していきます。
入社後に感じる「未経験の壁」4選

未経験からエンジニアとして働き始めた人の多くが、入社後に理想と現実のギャップに直面します。
ここでは、特につまずきやすい4つの「未経験の壁」を紹介します。
1. コードが書けるだけでは通用しない
学習段階で作っていた「Hello World」(※プログラミング初心者向けの教材として使われる画面に「Hallo,world!」などの文字列を表示するプログラムの総称)や簡単なToDoアプリのようなプログラミングは、実務ではほとんど通用しません。
業務でコードを書く際には、単に「動く」というだけでなく、「保守性」「パフォーマンス」「可読性」といった品質も求められます。さらに、チーム開発では自分以外の人が読むことを前提にしたコードを書く必要があり、独学だけでは身につきにくいスキルが問われます。
未経験エンジニアは、こうした「コードを書ける」というだけでは通用しない現実に直面する場合が多くなっています。
2. 技術選定や設計の思考が身についていない
実務の現場では、使用する技術やフレームワークは「なぜそれを選ぶのか」という背景を含めて議論されます。未経験者は「技術の使い方」だけに意識が向きがちですが、エンジニアとして成長するには「なぜその技術や仕組みを採用するのか」を考える設計的な視点が欠かせません。
実際の業務現場において議論に参加するためには、技術の背景や目的に目を向けることが必要になります。こうした点は独学では身に着けにくいため、入社後にギャップを感じることが多いようです。
3. タスク管理や報連相の難しさ
エンジニアの仕事は、個人作業だけで完結するものではありません。自分のタスクがチーム全体の進行にどう関わっているかを意識することが重要です。
しかし未経験者は、問題が起きても一人で抱え込みがちで、結果としてチーム全体のスケジュール遅延や品質低下を招いてしまうこともあります。小さな悩みでも早めに報告・相談する姿勢が求められます。
4. 学びの継続が前提の世界
IT業界は技術の移り変わりが激しく、現場では常に新しい知識が必要になります。「就職したらゴール」と考えていると、すぐに取り残されてしまいます。
むしろ入社してからが本当のスタートラインであり、自主的な学習を続ける姿勢が、長くエンジニアとして活躍するための鍵となります。向上心をもって学習を続けることで、新しい技術や知識を身に着けることができれば、成長し続けることができるチャンスが多い業界ということもできるでしょう。

入社後に実践すべき“技術力”と“仕事力”アップのコツ
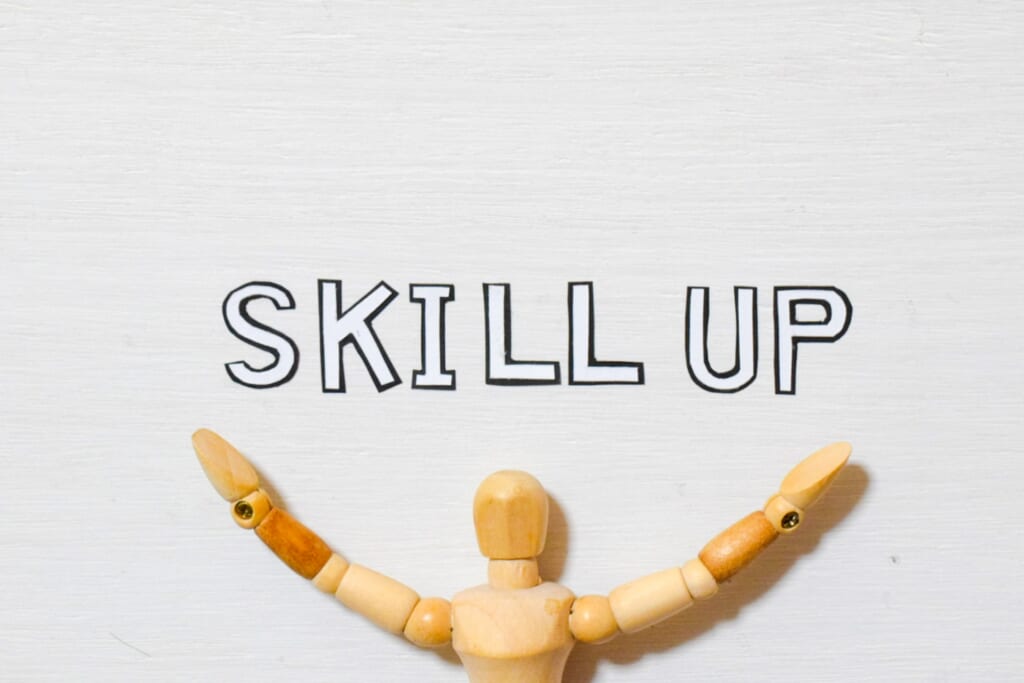
未経験からエンジニアとして現場で働くことになった場合に、求められるのは「技術力」だけではありません。チームのメンバーから信頼され、成果を出すためには「仕事力」「現場対応力」を身に着ける必要があります。
ここでは、未経験者からでも実践できる、業務現場で成長するための具体的なコツを紹介します。
小さくても確実に動くコードを書く
未経験のうちは、つい複雑な実装に挑戦したくなるものです。しかし、現場で求められるのは「確実に動く」コードを書く力です。そのためバグが出にくく、動作が予測できるシンプルなコードを心がけましょう。
シンプルであるほどテストしやすく、コードレビューもしやすくなります。複雑な処理よりも、安定して動作する小さな成果を積み上げることが、信頼と実力向上につながります。
「報告・連絡・相談」をエンジニア流に実践
エンジニアにとっての報連相は、Slackなどのツールを使った“こまめな共有”です。「今どこまで進んでいるか」「どこで詰まっているか」といった状況を、簡潔にでも伝える習慣を持つことで、メンバーや上長からのサポートを受けやすくなります。
たとえ遅れが出ていても、早めに伝えることでトラブルを未然に防ぐことができ、「この人はきちんと周囲と連携している」という評価も受けやすくなります。
レビューや指摘を前向きに受け止める
コードレビューは、単なるチェックではなく、成長のための貴重なフィードバックの機会です。指摘を受けたら「ありがとうございます」「次から気をつけます」と素直に受け止め、改善点をメモしておくことが大切です。
Notionなどに「指摘されたことリスト」をまとめ、定期的に振り返る習慣をつけると、同じミスを防ぐだけでなく、自身の成長も実感できるようになります。
ミーティングでの発言力と聞く力を伸ばす
未経験者にとって、会議で発言するのはハードルが高いものです。しかし「○○について確認させてください」と前置きするだけでも、質問のハードルはぐっと下がります。
また、発言が苦手でも、まずは「聞く力」を磨くところから始めましょう。相手の意図をくみ取り、会話の流れをつかむことができれば、次第に自信を持って発言できるようになります。また、朝会で「一つだけ質問する」ことを目標にしたり、議事録をとって共有するなど、小さな工夫を積み重ねることが後々大きな学びに変わります。
入社前に準備しておくと役立つこと

ここからは、入社前にやっておくことで、業務現場での戸惑いを減らすことができる準備を紹介します。
基本技術の習得は「感覚的に使える」レベルへ
HTML/CSS/JavaScriptなどの基本的な言語はもちろん、GitやAPI連携の仕組みも最低限の理解をしておくようにしましょう。
特にGitは、push/pull/branchといった操作を実務で頻繁に使います。「使い方を調べながら何とかできる」ではなく、「手が覚えている」状態にしておくことが理想です。実務で戸惑わないよう、日頃から練習しておきましょう。

チュートリアルだけでなく小さなアプリを1つ作ってみる
チュートリアルをなぞるだけでは実践力はなかなか身につきません。簡単なアプリで構わないので、自分の手で最初から最後まで作ってみましょう。
実際に作ることで、エラーへの対応力や構造への理解が深まり、就職活動時のポートフォリオにもなります。「自分でも作れるんだ」という自信にもつながるので、入社後の準備もかねて挑戦してみることをおすすめします。
技術用語を「人に説明できる」力をつける
エンジニアとして働くうえで、技術的なことをチーム内で説明する場面は意外と多くあります。たとえば「非同期通信って何?」「関数って何が便利?」といった基本概念を、誰かに説明するように話してみましょう。声に出して言語化するだけでも、自分の理解が曖昧な部分に気づき、実践的なスキルにつながります。
オンライン技術コミュニティに参加してみる
QiitaやZennで簡単な技術記事を書いてみたり、X(旧Twitter)やDiscordで現役エンジニアとやり取りするなどしておくことで、「自分もこの世界に入っていくんだ」という実感が湧いてきます。
文章で技術を発信すること自体が学びになることに加えて、将来的なネットワーク形成につながることもあります。
「わからないことリスト」をつくり、整理して質問できる習慣をつける
現場では「何がわからないか」を明確に伝える力が問われます。そのためには、普段から自分の「つまずきポイント」や「学んだこと」を整理しておくことが大切です。Notionやメモアプリで“学びログ”をつけておくと、復習にもなり、質問力の向上にもつながります。
開発ツールに慣れておく
現場ではVSCodeやSlack、GitHubといったツールを日常的に使います。特にSlackでのやり取りや、VSCodeでのファイル管理に慣れていないと、周囲と基本的なやりとりができず、不安感やつまずきを感じやすくなってしまいます。
エンジニア同士で利用されることが多いツールは、事前にインストールし少しでも触って慣れておけば安心でしょう。
入ってから後悔しないための企業選びのコツ

未経験からエンジニアとしてキャリアをスタートさせる場合、会社選びはその後の成長スピードや働きやすさに大きく影響します。「未経験歓迎」と書かれていても、いざ入社してみると放置されたり、開発どころか保守業務しかさせてもらえなかった…という声も少なくありません。
ここでは、入社後に後悔しないための企業選びのポイントを解説します。
1. 学習サポートや研修制度の有無を確認
未経験からエンジニアとしてのキャリアを積み重ねていくにあたっては、適切な学習環境が不可欠です。「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」だけに頼る企業よりも、外部研修の受講支援や、社内勉強会などの制度が整っている企業の方が、体系的にスキルを伸ばしやすい傾向にあります。
特に注意したいのは、募集要項では「未経験歓迎」と掲げながら、実際には教育リソースがほとんど用意されていない企業です。こうした企業を避けるためにも面接の際には、研修内容や教育体制について具体的に質問し、「どんなサポートがあるのか」「どれくらいの期間で実務に入るのか」などを確認するとよいでしょう。
また、エンジニアを取り巻く企業風土も重要といえます。例えば、副業が容認されている企業は、社員が自分のスキルを社外で試すことを支援する風土があり、成長意欲のある若手にとって魅力的といえます。また、QiitaやZennなどでの技術発信を奨励している企業は、エンジニアのスキルアップやコミュニティ支援に理解があり、「人を育てる文化がある」と考えることが出来るでしょう。
2. チーム構成や開発体制をチェック
未経験者がスムーズに業務に慣れるためには、メンバーや上長のサポートが不可欠です。そのため、いきなり一人でアプリ開発を任されるような環境は、スキル・メンタルが対応できず、挫折の原因になります。採用ページや面接などで、チームの開発体制やメンター制度の有無、ベテランエンジニアの在籍状況を確認しましょう。
また、レビュー文化があるかどうかも大切なポイントです。コードレビューが習慣化されている環境では、自身の間違いに気づくことができるだけでなく、より良い書き方や考え方を吸収することができます。
3. 現場エンジニアと話すことができる面談の機会を設けてもらう
面接の場では、できる限り現場のエンジニアと話す機会をもらいましょう。カジュアル面談などで「実際に未経験から入社した人がどう育っているか」「1日の業務の流れ」「新人がどんなサポートを受けているか」などを聞くことができれば、その会社で働くイメージが具体的になります。
表面的な制度よりも、現場の“温度感”を知ることが、企業選びの精度を高めてくれるでしょう。
4. 口コミサイトやSNSで内部の雰囲気を調べる
企業風土や会社の雰囲気を知る上では、転職会議、OpenWork、X(旧Twitter)などの口コミや投稿も参考にするとよいでしょう。こうしたサイトでは、実際に働いている(いた)人の声から、研修・教育制度や福利厚生、社内の雰囲気、上司との関係性などを集めることができます。
ただし、人によって感じ方は異なるため、すべての情報を鵜呑みにすることは避けるべきです。極端な意見もあるため、複数の情報を収集したうえで参考程度に考えるようにするとよいでしょう。
5. 最初の会社は“キャリアのスタート地点”と考える
自身が未経験の状態から、すべての条件がそろった理想的な会社を見つけるのは困難です。しかし、「この会社で自身の希望する技術を学べそうか」「次のステップにつながるか」という視点で考えれば、適切な選択をしやすくなります。
未経験からのエンジニア転職であれば、最初の会社はあくまで“スタート地点”といえます。長く働くかどうかにこだわるより、自分がエンジニアとして成長できる環境かどうかを見極めることが、将来の後悔を減らすポイントといえるでしょう。
未経験エンジニアの転職ならUnitas(ユニタス)
未経験からエンジニアを目指すなら、サポート体制が充実した「Unitas(ユニタス)」が心強い味方になります。ユニタスは、IT業界へのキャリアチェンジを支援する転職エージェントで、未経験者向けの無料プログラム「UnitasDojo(ユニタス道場)」も提供しています。
UnitasDojoでは、javaをメインに基礎から実践的な開発スキルまでを習得可能となっています。オンラインでベテランエンジニアの指導を受けることが出来る点も魅力です。学習後には、キャリア支援と企業紹介も受けられるため、「学ぶ→働く」までを一貫してサポートを受けることが出来ます。
事前に選考はあるものの本気でエンジニアを目指す人をサポートすることを目的としているため、まずは説明会で話を聞いてみるとよいでしょう。Unitas(ユニタス)を利用することで、未経験からエンジニアに挑戦するための第一歩を安心して踏み出すことができます。
適切な準備で未経験エンジニアの「壁」を乗り越えよう
これまで解説してきたように未経験からエンジニアを目指すのは、決して簡単なことではありません。転職できたとしても入社後に、ギャップを感じて理想通りのキャリアを積むことが出来ない場合もあります。
しかし、正しく学び、適切な準備を行うことで、リスクを低減し、自身にあった会社とスキルアップの環境を選択することができます。自分にあった環境を選ぶことができれば、今感じている不安も、未来の成長の種に変わるはずです。
Unitas(ユニタス)のような経験豊富なパートナーのサポートを受けながら焦らず、着実に、自分のペースで進んでいきましょう。そうすれば、未経験からのエンジニア転職にも明るい未来が開けるでしょう。