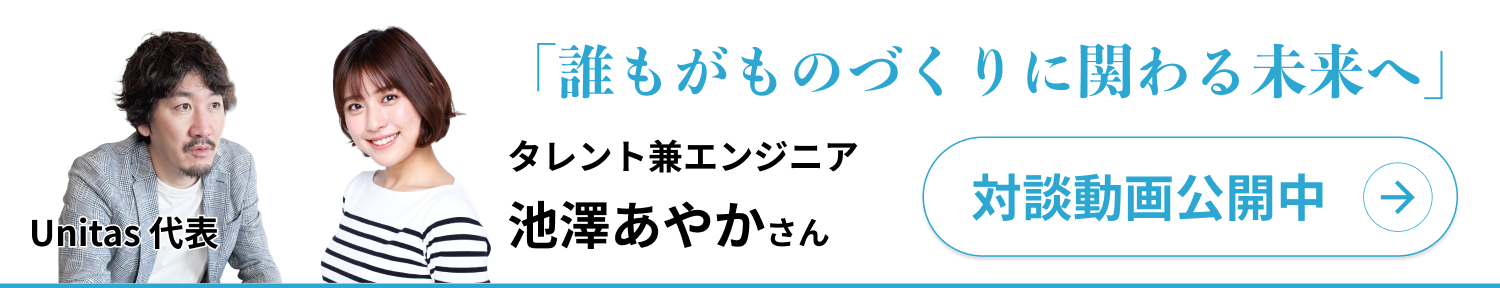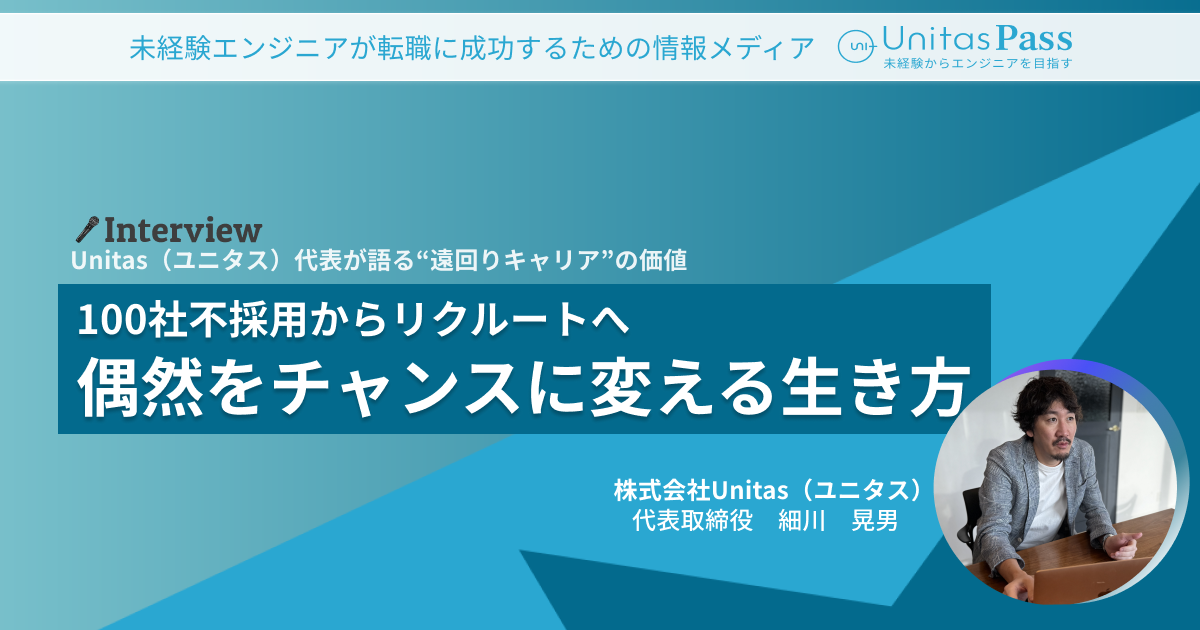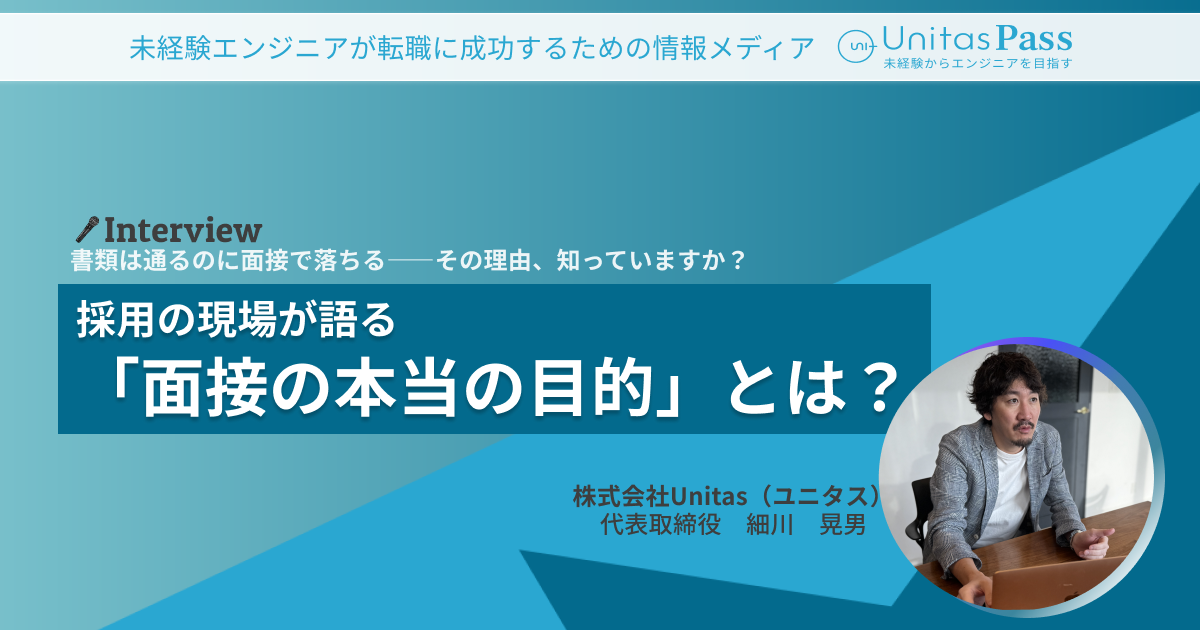【スペシャル対談】池澤あやかとUnitas(ユニタス)代表が語る!誰でも”ものづくり”できる未来へ (PART1)

今回は、エンジニア兼タレントの池澤あやかさんと、未経験エンジニアのキャリア支援を手がける株式会社Unitas(ユニタス)の細川代表のスペシャル対談です。テーマは「誰でもものづくりに関われる未来について」。前半では、お二人の学びやキャリア形成の経験を軸に、コミュニケーション能力や好奇心など、今のIT現場で求められる素質についてお聞きしました。
タレントとエンジニア、二つの顔をもつ池澤さん

― 本日はUnitas(ユニタス)の代表細川さん、そしてタレント活動と並行してエンジニアとしても活躍されている池澤あやかさんをお迎えしています。まずは自己紹介からお願いします。
池澤:はじめまして。池澤あやかと申します。現在はIT企業でソフトウェアエンジニアとして働きながら、副業としてタレント活動も続けています。中学2年生のときに「東宝シンデレラオーディション」に応募したことがきっかけで、情報系のテレビ番組に出演したり、イベントでの登壇などを行っています。
細川:Unitas(ユニタス)代表の細川です。弊社のメイン事業は人材紹介で、特にエンジニアに特化した転職支援を行っています。
私自身はエンジニアに直接関わる経歴ではありません。前職はリクルートで、13年間「ホットペッパーグルメ」で飲食店向けの営業をして、その後人事部に異動し、採用や研修、組織開発など人事領域の責任者をしていました。これらの経験を経て、現在の会社を立ち上げ、4年目に突入しています。
池澤:エンジニアと接点はなかったのに、どうしてエンジニア特化型の人材サービスを作ろうと思われたのですか?
細川:もともと、私が営業出身、共同創業者がエンジニア出身ということもあり、最初は営業とエンジニア、両方の領域で人材紹介をしていこうと考えていました。でも、実際に事業を進めていくと、自然とエンジニア希望の方が多く集まるようになったんです。さらに、経験者だけでなく、未経験からエンジニアを目指す方も多くいらっしゃいました。
そこで、「せっかくならこの領域に特化しよう」という流れになり、未経験エンジニア向けの転職支援に力を入れるようになりました。
池澤:確かにエンジニアは流動性が高いというか、転職する方がとても多い業界だと感じています。
― 池澤さんはいつからプログラミングを始められたんですか?
池澤:本格的に学び始めたのは大学に入って授業でプログラミングを学ぶようになってからです。大学でインタラクションデザインの研究をしていましたが、電子工作とプログラミングが必須で、 プログラミングを習得するのにとても苦戦しました。
細川:プログラミングを勉強するのは大変ですよね。どうやって習得されたのですか。
池澤:普段はProcessingやopenFrameworksなど、C++やJavaに近い言語を使って装置を作ったりしていて、あまりプログラミングを理解していませんでした。そこで当時、「Ruby合宿」というプログラミング合宿が格安で開催されていたので、そこに参加したんです。
結果的にこの合宿がすごく良くて、「Ruby on Rails」が当時すごく流行っていたこともあって、「これはWeb系にも活かせるな」と感じました。
もともとWeb制作にも興味があったので、そっちも勉強してみようと自然な流れで学びの幅が広がっていきました。振り返ると、そうやって興味のあることからどんどんつながっていったのが、自分の成長のきっかけだったと感じています。
大学卒業後はタレント活動も並行して「Web制作とタレント、2つ合わせればやっていけそう」と思い、その2本柱で活動を続けていました。
その後、知り合いから声をかけられたのがきっかけで、バックエンドの業務も担当するようになり、ソフトウェアエンジニアへとシフトしていきました。関わっていた会社が事業終了することになったタイミングで、「初めて転職してみようか」と、30歳で初めて正社員としてIT企業に入社して今に至ります。

エンジニアに向いている人の特徴
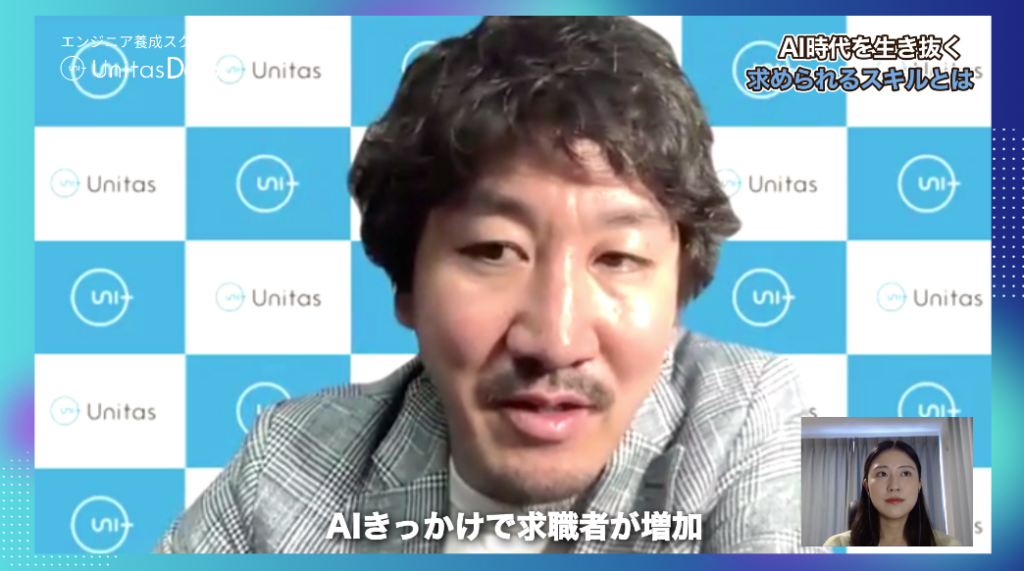
― Stokke(ストッケ)の部品を3Dプリンターで制作したというX(旧Twitter)の投稿を見て、池澤さんは「ものづくりがお好きなんだろうな」と感じていました。
池澤:Stokke(ストッケ)って子ども用の椅子なんですけど、そのパーツがちょうど家になかったので、ネットで3Dプリント用のデータをダウンロードして、自宅の3Dプリンターで出力してみたんです。
細川:私は、未経験からエンジニアを目指して、実際に活躍される方に共通しているのは「ものづくりが好き」というマインドを持っていることだと思っています。自分の手で何かを作り上げることに楽しさを感じられる方は、エンジニアの仕事にも自然と馴染んでいけるんですよね。
池澤:確かにものづくり好きな方で活躍しているエンジニアは多いですね。ものづくりが好きな方、または、技術やコンピューターが好きな方はエンジニアの適性があると思います。

― 細川さんは他にどのような方がエンジニア向きだと思いますか?
細川:以前、大手SES企業の依頼で「活躍しているエンジニアの共通点を洗い出して、採用要件を定義してほしい」というプロジェクトがありました。その際、実際に現場で活躍しているエンジニアの方を10名ほどピックアップして、インタビューを行いました。
その中で印象的だったのが、「コミュニケーション能力」や「社交性」といった、人との関わり方に関する要素が多く挙がったことでした。自分から他の人に話しかけたり、自然とチームに溶け込んでいけるような方が、活躍している傾向が強いというのが、インタビューから見えてきました。
池澤:それは私も日々感じていることです。よく「エンジニアは一人で黙々と作業できれば大丈夫」とか、「ちょっと変わっていても問題ない」なんてイメージを持たれることもあると思うんですが、実際はチームで動くことが多いので、人とのやり取りがとても大切なんですよ。
実際に、ちょっと言い方がキツい人が一人いるだけで、職場の雰囲気が悪くなって、辞めてしまう人が続く…なんてこともあります。エンジニアって比較的転職しやすい職種なので、人間関係がうまくいかないと、あっという間にメンバーが減ってしまうこともあるんですよね。
細川:さきほどの話の続きですが、活躍している人に共通する要素には「好奇心」の要素も多く上がりました。「好きこそ物の上手なれ」じゃないですけど、ベースに「面白い」「もっと知りたい」という気持ちがないと、知識やスキルもなかなか広がっていかないのかなと。
IT業界は変化がとても激しい業界なので、ちょっとした空き時間にも新しいことを調べてみたり、自然と技術に興味を持てる人は、成長が早いんですよね。その意味でも、好奇心は成長に欠かせない要素なんだなと感じました。
池澤:そうですね。技術の流れが早いので、保守的だと結構難しいかもしれないです。私も、WebやXで話題になっている新しいものをなるべくチェックするように心がけています。あとは、友人たちが最近どのようなことに取り組んでいるのかを聞いたり、そこから興味を広げていったりもしています。
何か作っていく過程で、「ここは、もっとちゃんと学ばなきゃ」と感じることも多いので、必要に応じて、わからないことがあったら、その度にキャッチアップしながら学んでいくスタイルが自分には合っているかなと思っています。
細川:なるほど。知らないことを自分で探求していく力、好奇心や探求心みたいなものは、エンジニアを目指す上ではすごく大事な資質なんだろうなと感じますね。
実は僕自身、あまり調べることが得意じゃなかったり、好きじゃなかったりするんですよね。だからこそ、自分はあまりエンジニアに向いていないのかなと思っています(笑)。
AI時代に求められる“学ぶ力”

― 最近では、ChatGPTをはじめとするAIツールもかなり浸透してきました。これからの「AI時代における学び」についても、聞いてみたいと思っています。池澤さん自身、学び方の変化について何か感じていることはありますか?
池澤:今は「AIといかにうまく共存できるか」という視点が、学びにおいても仕事においてもすごく重要になっていると感じます。
「これを作ってみたい」と思ったときに、以前ならまず参考書を一通り読んでから取りかかる、というのが一般的だったかもしれません。でも、いまはAIと会話しながら、考えを整理したり、わからない部分を一緒に言語化しながら、学んでいくことができます。
― 技術を活用して、自分も成長していくやり方ですね。最近では利用できるAIツールも増えていますが、上手な活用法はありますか?
池澤:まずは、話題になったものを触ってみて、自分の仕事に活かせるかどうか試すことですね。最近だと、「Claude 3.7 Sonnet」のような、コーディングに強いAIモデルが話題です。 私も他の人が使ってみた感想や議論をネットで見て、「ちょっと触ってみようかな」と思って試してみました。
実際に使ってみると、これが結構使えるという手応えがありました。なので、これからはAIと一緒にコードを書きながら、さらにスキルを伸ばしていく時代になっていくのかなと感じています。
細川:なるほど、話題になったものをすぐ使ってみるっていうのはすごい大事な観点ですよね。基礎をしっかり学ぶことと、プラスして話題になるものをまずやってみて、自分に合うかというか、使えるかどうか試すのが大事ということですね。
池澤:はい。その中で感じてるのは、やはりプログラミングの基礎が大切ということです。私はもともとバックエンド開発をメインにしてきたのですが、最近ではフロントエンドにも少しずつ携わるようになりました。フロントエンドについても、AIと連携しながら取り組めば、自分でもしっかり書けるんです。
これはバックエンド開発の基礎をしっかり学んできたからだと思います。「基礎を身につけた上で、AIと一緒に応用していく」という意識が、今の学び方や働き方の軸になっています。
― ちなみに細川さんは、企業の方々と直接お話しする機会も多いと思うのですが、企業や転職市場において、AIの登場による変化は感じていますか?
細川:明らかな変化として感じているのは二つあります。 一つ目は、やはりAIブームをきっかけに、エンジニアを目指す求職者の数が増えたということです。AIエンジニアを採用したいという企業の動きも目立ち始めました。
二つ目は、最近「プロンプトエンジニア」と呼ばれる、AIに指示を出す役割の人材を求める企業が少しずつ増えつつあることです。
ただ、未経験層で求められるスキルに関しては、大きな変化は今のところそれほど感じていません。基本的にはJavaなど、基本的なプログラミング言語をしっかり勉強しているかという点と、新しい環境に適応できる社交性や、他者との円滑なコミュニケーション能力がとれることが求められています。